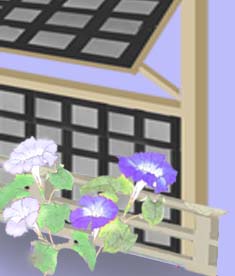 能 「半 蔀 ーはじとみ」
能 「半 蔀 ーはじとみ」
詞章と現代語訳
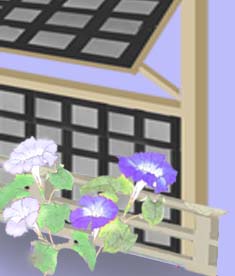 能 「半 蔀 ーはじとみ」
能 「半 蔀 ーはじとみ」
詞章と現代語訳
能楽 : 「半 蔀」 …… はじとみ 作者 : 内藤藤左衛門か。素材 : 「源氏物語」 夕顔の巻
登場人物 : シテ……女(夕顔の精) ワキ……僧 アイ…… 所の者
後シテ……夕顔
あらすじ雲林院の僧が夏の修行の終わりに花の供養をする。そこに一人の女が現れ、花を献じ、花の陰に消え失せる。それは夕顔の上の亡霊であった。
五条あたりに赴いた僧の前に、半蔀屋から夕顔が現れ、光源氏との恋を語り始め、夕顔の花を源氏に差し上げたことが、機縁だった……」と述べ、舞を舞った後、再び姿を消す。
謡 曲「 半 蔀 」詞 章
ワキ詞「これは都紫野雲林院に住居する僧にて候
さてもわれ一夏の間花を立て候
はや安居も過方になり候へば 色よき花を集め
花の供養を執り行はばやと 存じ候
敬つて白す立花供養の事
右非情 草木たりといへども
此花広林に開けたり 豈心なしといはんや
なかんづく泥を 出でし蓮
さて、この一夏の間、花を立てて、仏に手向けました。
もはや安居も終わりの頃になりましたので、色の良い花を集め
花の供養を執り行おうと思います。
謹んで花の供養を行うことを申し上げる。
花は感情を持たない草木であるけれど、
この花は、広い大地に咲くものである。どうして心ないものとして、扱うことができようか。
特に、泥中に生える蓮の花は、
一乗妙典の題目たり この結 縁に引かれ
草木国土悉皆成仏道
シテ「手に取ればたぶさに穢る立てながら
三世 の仏に花奉る
ワキ詞「不思議やな今までは 草花りよようとして
見えつる中に 白き花のおのれ独り笑の眉を開けたる は
いかなる花を立てけるぞ
妙法蓮華経の経典の題目である。この仏の縁の引かれ、 草木も国土も悉く皆、成仏することである。
(里の女が登場する。常座に立って謡いだす。)
女「手に折りとると、その手によって汚れるので、そのまま、
三世の仏に花を手向け申し上げる。
僧「不思議なこと。今までは草花が何となく見えていたが、
見える中に、白い花が自分だけ微笑んでいるのは、
一体、どういう花を立てたのか
シテ「愚の御僧の仰やなたそがれ時のをりなるに
などかはそれと御覧ぜざる さりながら
名は人めきて賎しき垣ほにかゝりたれば
知しめさぬば理なり
これは夕顔 の花にて候。
ワキ「げに/\さぞと夕顔の花の主はいかなる人ぞ
女「愚かなことを仰せの僧です。黄昏の折なのに、 なぜかそれとお分かりにならないか。しかしながら、
その花の名は人の名めいていて、卑しい家の垣に這いかかっているのだから、
お分かりにならないのは、尤もであります。
これは夕顔の花でございます。
僧「なるほどそうだ、夕顔の花の主人はどういう人か。
シテ「名のらずと終には知しめさるべし
われはこの花の蔭より参りたり
ワキ「さては此世に亡き人の 花の供養に逢はんためか
それ につけても名のり給へ
シテ「名はありながら亡き跡になりし昔の物語
ワキ「何某の院にも シテ「常はさむらふ真には
地「五条あたりと夕顔の /\
空目せし まに夢となり
面影ばかり亡き跡の立花の蔭に隠れけり/\
女「名のらなくても、やがてお分かりになるだろう。私はこの花の陰から参りました。 僧「それではこの世に亡きひとが、花の供養に逢うために来られたのか。
それにしても、名を名のりなさい。
女「名はあるのだけれど、今はこの世に亡き身となり、すでに昔の物語
僧「何某の院にも、 僧「常に伺候していたが、真実は、
地「五条あたりに住んでいた者だと言って、
脇見をした間に、まるで夢のように、夕顔の花の
面影として、亡き身をこの世に残しただけで、
立てかけられた花の陰に隠れて見えなくなってしまいました。
中入
ワキ「ありし教に従つて 五条あたりに来て見れば
げにも昔の座所 さながら やどりも夕顔の
瓢箪しば/\空し 草顔淵が巷に滋し
後シテ「藜〓深く鎖せり
夕陽のざんせい新に窓を穿つて去る
中入
僧「さきほど教えられたように、五条あたりに来てみれば、
本当に昔おいでになった所が、そのままで、家には夕顔も
昔とおり『瓢箪しばし空し、草顔淵が巷に滋し』の詩のような
有様だ。
夕顔「あかざが深く茂って、戸口を閉ざしている。
夕日の光がさっと差し、窓を通して入り、やがて消える。
地「しうたんの泉の声 シテ「雨原憲が樞を湿す
下歌地「さらでも袖を湿すは 廬山の雪の曙
窓東に向ふ朗月は /\
琴榻にあたり しう上の秋の山 物凄の気色や
ロンギ「げに物凄き風の音 簀戸の竹垣ありし世の
夢の姿を見せ給へ 菩提をふかくとむらはん
シテ「山の端の 心も知 らで行く月は
上の空にて絶えし跡の 又いつか逢ふべき
地謡「泉の音がして、 夕顔「『雨原憲が枢を湿す』という趣。地謡「雨だけでなく涙も袖を濡らすのは、かの雪の曙で名高い廬山の草庵でのこと。
東の窓の向こうの澄んだ月の光は、
琴の榻(しじ)を照らし、垣根の上の秋の山、物凄く寂しい感じがする。 僧が弔いをしようと言うと、半蔀を上げて、夕顔が姿を現す。
地謡・僧「誠に物凄く寂しい風が、竹の透垣に音を立てている
どうぞこの世で、夢のお姿をお見せください。菩提を深く弔いましょう。
夕顔「かつて、『山の端の心も知らで行く月は 上の空にて影や絶えなん』と詠んだが、また何時かあの方にお逢いできることがあろうぞ。
地「山賎の 垣は荒る ときをり/\は
シテ「哀をかけよ撫子の 地「花の姿をまみえなば
シテ「跡訪ふべ きか 地「なか/\に
シテ「さらばと思ひ夕顔の
地「草の半蔀おし上げて 立ち出づる御姿見るに涙の留まらず
クセ「其頃源氏の中将と聞えしは 此夕顔の草枕
たゞ仮臥の夜もすがら 隣を聞けば三吉野や
御嶽精進の御声にて
南無当来導師 弥勒仏とぞ称へける
地謡「それにしても、『山賤の垣穂荒るとも 折々は、夕顔「あはれをかけよ 撫子の露』ともお願いしたいのであるが
地謡「あわれな花の姿をお見せするなら、
夕顔「亡き跡を弔ってくださいますか。
地謡・僧「もとよりそれは、当然のこと。
夕顔「それではと思って、夕顔の、
地謡「草の葉で覆われた半蔀を押し上げて、立ち出ておいでになる その御姿を、拝見すると、涙が留まらず、
地謡・夕顔「その頃、源氏の中将と申し上げた方は、この夕顔の草深い宿で、
ただかりそめの一夜を過ごされ、隣の家から聞こえてきたのは、
み吉野の金峰山参りの行者の精進の声で、
『南無当来導師、弥勒仏』と、唱えていた。
今 も尊き御供養に其時の思ひ出でられて
そぞろに濡るゝ袂かな 猶それよりも忘れぬは
源氏この宿を 見初め給ひし夕つ方
惟光を招きよせ あの花折れと宣へば
白き扇のつまいたうこがしたりしに
此花を折りて参らする
シテ「源氏つ くづくと御覧じて
今、尊いお供養を受けるにつけても、その時のことが思い出されて、そぞろに涙で袂の濡れる。猶、それよりも忘れられないのは、
源氏がこの宿を初めておいでになった夕方、
惟光を招き寄せ、あの花を折れと仰いますと、
白い扇の端に、香を焚きしめたものに、
この花を手折って、差し上げました。
夕顔「源氏はつくづくご覧になって、
地「うち渡す遠方人に 問ふとても
それ某花と答へずば 終に 知らでもあるべきに
逢ひに扇を手に触 るゝ 契の程の嬉しさ
折々尋ねよるならば 定めぬ海士の此宿の
主を誰と白浪の よるべの末を頼まんと
一首を詠じおはします 折りてこそ
序ノ舞
地謡「そこの方にお尋ね申す』と仰ったのだが、そのとき、夕顔の花と答えなかったならば、結局ご縁がなかったものを、
私の扇を手にお取りになり、契りが結ばれたのは嬉しいこと。
折々、尋ね寄るならば、『行方定めぬ海士』のこの宿の、
主が誰と分からなくても、末永く通う所にしようと、源氏は、
一首をお詠みになりました。
序ノ舞 夕顔は舞を舞い、やがて半蔀の中に入り、姿は消えてしまう。
シテワキ「折りてこそそれかとも見め 地「たそがれに
地「ほのぼの見えし 花の夕顔/\/\
シテ「終の宿は知らせ申しつ
地「常にはとむらひ
シテ「おはしませと 地「木綿付の鳥の音
シテ「鐘も頻に
地「告げ渡る東雲 あさまにもなりぬべし
明けぬ先にと夕顔の明けぬ 先にと夕顔のやどりの
また半蔀の内に 入りて其まゝ夢とぞ なりにける
夕顔「折りてこそ それかとも見め 地謡「たそがれに
地謡「ほのぼの見えし 花の夕顔
夕顔「私の最後の住まいは、お知らせ申しました。
地謡「どうぞ、いつもお弔い 夕顔「くださいませ……と、
地謡「もはや鶏の鳴く声がして
夕顔「鐘もしきりに鳴って、
地謡「夜明けを告げている。朝になり恥ずかしいことになるだろう。
明けない前にお暇をとり、夕顔の宿の
また半蔀の中に入って、(姿は消え)
僧の夢の中の出来事になってしまいました。
参考:日本古典文学全集(小学館)