要約ー源氏物語 (4) 若菜上~下(第34帖~第35帖) (源氏の君には女三の宮が降嫁され、その愛らしい姿に柏木は・・・) |
|---|
| 若菜(わかな)上 ー第三十四帖 朱雀院はこの頃ずっとご病気がちでございました。すっかり気弱になられて、出家したいという気持がなお一層強くなられ、その準備とし  て西山に御寺を完成させなさいました。 て西山に御寺を完成させなさいました。この院の御子は、東宮のほかに女宮が四人おいでになりました。その中の女三宮(おんなさんのみや)には、これと言ったご後見がありませんので、院は不憫にお思いになり、格別に可愛がっておられました。御年も十三歳ほどになられましたので、御裳着(もぎ)の儀式(成人式)をお考えになり、その将来を大層心配なさっておられました。 ある日、東宮が父院をお見舞いなさいました。大層ご立派に成人された東宮のご様子を、誠に頼もしくご覧になりました。 朱雀院は、 「この世に不満に思うことは何もありません。ただ女三宮はまだ幼く、私一人を頼りとしてきましたので、私が出家した後に心細い生活をするのだろうかと、誠に気がかりで悲しく思っております……」と、涙を拭いながら仰せになりました。 年が暮れていくにつれて、ご病気も一層重くなられ「やはり最期か……」とお思いになりました。その優しいお人柄ゆえ、皆は大層悲しんでおりました。 その年が暮れ、権中納言(夕霧)も,源氏の君の言葉を携えて、お見舞いにおいでになりました。院は御簾の中に招き入れて、親しくお話をなさいました。 「桐壺院がご臨終の折、多くのご遺言を残されましたのに、事の行き違いから六条の大殿(源氏の君)には辛い思いをおさせ申したにも拘わらず、その恨みが残っているご様子さえもお見せにならず、東宮などにも親しくお仕え下さるのは、誠に有り難いことです……」と、涙ながらに仰せになりました。権中納言は、 「過ぎ去りました昔の事は、私には分かり難いことで、父君は辛い事をほのめかされることもありませんでした。院が御退位なさって静かにお暮らしの今こそ、心置きなくお話を承りたいと存じながら、つい月日が過ぎてしまい……」と奏上なさる夕霧は、二十歳にも足りない年齢ですのに、誠にご立派で輝くばかり美しくおられました。 院は女三宮の御後見として、この人こそとお考えになりましたが、夕霧は、 「まだ頼りにならない私には、妻も得難うございます」とお答えなさいました。 ある日、院は乳母(めのと)たちをお呼びになり、女三宮の御裳着(もぎ)の事などを細々と指示なさいました。その折に、 「六条院の大殿が昔、兵部卿(ひょうぶきょう)の娘(紫上)を育て上げたように、誰かこの姫宮を引き取って育てて下さる人がいないものか……権中納言(夕霧)が将来有望なので、独身の頃に申し入れてみるべきだったのだが……」と申しなさいました。 乳母は、 「確かに権中納言は真面目な方ですが、雲居の雁お一人だけを想い、他の女性に心を移すことさえありません。実はその父・大殿こそが、今も女性にご関心をお持ちで、今でも前斎宮にお便りを差し上げていると聞いております」とお答え申し上げますと、 「その好色心が心配なのだ。……では親代わりとして、姫宮をお譲りすることにしよう。六条の大殿は信頼出来る人物で、この人をおいて後見役に適当な人はありません。 兵部卿宮(ひょうぶきょうのみや)は同じ皇族なので軽んじるべきではないが、あまりにも頼りない。 衛門(えもん)の督(かみ)(太政大臣の息子)が、内親王でなければ妻にしない……と、自ら女三宮の後見を希望しているようだが、まだ若くてあまりにも軽い地位である。理想は高く将来を期待できるが、やはり婿としては不十分であり……」等と、大層心悩ませておいでになりました。 権中納言もこの噂をお聞きになり、 「先日、院が直々に、私に意中をお漏らしになったことを思えば、心ときめく事であるけれど、これほど高貴な姫宮と結婚したなら、左右に気遣って、自分も苦しい立場になることだろう。しかし他人のものに決るのも残念なことだ」とお思いでございました。 東宮はいろいろお考えになり、 「やはりあの六条の大殿にこそ、親代わりとして女三宮をお譲りするように……」と、御内意がありましたので、院はますます御決心を固めなさいました。まずは弁を遣わし、その事情をお伝えなさいました。 源氏の君は、 「院のご寿命を考えますとお気の毒とは存じますが、私とてどれほど長く生きられるものか……。姫宮のご後見をお引き受けすることに不安を覚えます。今後は女三宮を格別にご養育申し上げ、やはり帝に差し上げるのがよろしいかと存じます……」とお答えなさいました。けれども御心の中では、 「女三宮の母は、あの藤壷の姉君だから、きっと美しい姫宮に違いない。これもまた何かの深い御縁か……」と感慨深くおられました。 やがて年も暮れました。朱雀院には快方に向かうご様子も見えませんので、慌ただしく女三宮の御裳着の儀式をなさいました。院の御催事もこれが最後かと、帝も東宮も大層お気遣いなさいまして、豪華に光り眩しい程に、蔵人所や納殿の舶来品などを献上させなさいました。六条院からも御祝儀などが盛大にありました。 中宮は、昔、斎宮として伊勢に下る儀式の時に、院から御櫛を頂戴し、好意をお寄せ頂いたことを思い出し、特別に見事な御櫛を作らせて、姫宮にお贈りなさいました。 さしつぎに見るものにもが万世を 黄楊の小櫛の神さぶるまで (朱雀院) (訳)挿し続けて姫宮の万世を見たいものです。黄楊の小櫛が古くなるまで…… 御裳着の儀式が終わり三日ほどが過ぎて、朱雀院は遂に御髪を下ろされました。御后方は大層悲しまれ、特に尚侍(かん)の君(朧月夜)はお側を離れずに涙を流しておられました。 「この悲しい別れが耐え難いことよ……」と、院はご決心が鈍ってしまいそうでしたが、大層苦しそうなご様子のまま、この俗世と別れる儀式を済ませなさいました。 六条の大殿がお見舞いに参上なさいました。朱雀院はご気分が悪いのを我慢なさってお逢いになり、大層弱々しく、 「出家しても余生がなければ、勤行の意志も果たせそうにありませんが、せめて念仏だけでも勤めたいと思っております。ただ内親王たちを残していくことが気がかりで、特に後見のない女三宮を……」と仰せになりました。 源氏の君は、 「誠に内親王の御ためには、ご後見に当たる者はやはり、夫婦の契りを交わしてお世話申し上げるのが安心なことでございます。」と奏上なさいました。院は、 「この俗世を離れる時になって、捨て去りがたい事が誠に多く……病気は日々重くなってゆきます。恐縮なお譲り事なのですが、この幼い内親王一人を特別に目をかけお育て下さって、適当な婿をも貴方のお考え通りにお決め下さい。権中納言(夕霧)が独身でいた頃に、お願いすべきであった……」と申されました。 源氏の君は恐縮して、 「権中納言は何分にもまだ経験が浅く、頼りなく思われます。……畏れ多いことですが、私が真心を尽くしてご後見させていただきましょう。ただ老い先短いことが懸念されますが……」と、遂に後見をお引き受けなさいました。 夜が更けて源氏の君はお帰りになりましたが、院は今夜の冷たい雪にお風邪を召され、一層苦しそうになられました。けれどもこの女三宮のご将来をお決めになりましたので、やっとご安心なさったのでございました。 六条院に戻られた源氏の君は、誠に気が重く、思い悩んでおられました。紫上のお気持を思うととても辛くなられ、 「院が大層お弱りになりお見舞いに参上しますと、胸打たれる思いがいたしました。院は、この私に女三宮の後見役をお頼みになり、悲しみ深い親心を語り続けられましたので、すげなくご辞退申し上げることができませんでした。やがて六条院にこの姫宮をお迎えすることになりましょう。……貴女には誠に不愉快なことでしょうが、皆で穏やかに、姫宮をお世話申し上げましょう……」とお話しなさいました。 紫上は、 「誠にお気の毒なご依頼で……。私をお咎めでなければ、このままここに居させていただきましょう。御母女御(藤壷の姉)の御縁から言っても、仲良くしていただけるでしょうから……」と謙遜なさいました。紫上は表面上とても穏やかに振る舞っておいでになりましたが、御心の内ではご将来のことなどを憂い、心乱れておられました。  年が改まり、源氏の君は四十の御賀を迎えられます。朝廷でも祝宴が盛大に催されると評判でしたけれど、源氏の君は厳めしい儀式など嫌いなご性格ですので、これを辞退なさいました。 年が改まり、源氏の君は四十の御賀を迎えられます。朝廷でも祝宴が盛大に催されると評判でしたけれど、源氏の君は厳めしい儀式など嫌いなご性格ですので、これを辞退なさいました。正月子(ね)の日に、左大将の北の方(玉鬘)が若菜を献上されました。内密に準備なさいましたので、辞退もなされず、内々の御賀でありながら、大層格別に催されました。 小松原すえの齢に引かれとや 野辺の若菜も年を積むべき (訳)小松原の将来のある齢に引かれ 野辺の若菜も長生きするでしょう 御盃が下され、若菜の羮(あつもの)(吸物)を召し上がりました。太政大臣が管楽器などを揃えましたので、内輪の管弦の遊びながら、この上なく素晴らしいものになりました。 如月十日過ぎ、遂に朱雀院の姫宮(女三宮)が六条院の源氏の君のもとに降嫁なさいました。こちらの院ではその準備に心尽くされ、南殿の西対や渡殿にかけて念入りに飾らせなさいまして、御結婚の儀式はこの上なく盛大に行われました。 紫上は何事にも平静を装って、お輿入れの時にも細々とお世話なさいますので、源氏の君はますます得難い方だといとおしくお思いになりました。 なるほど、この姫宮はまだとても子供で、ただあどけないご様子でした。源氏の君は昔、あの紫のゆかりの少女(若紫)を北山で見つけた時の事を思い出されて、ただ幼いだけの姫宮を「何と張り合いのないことか……」とご覧になりました。 三日間は毎晩、姫宮のところにお通いになる慣わしですのに、紫上が君のお召物に香を焚きしめながら、物思いに沈んでおられる様子を大層いじらしい……とご覧になって、 「どんな事情があるにせよ、他に妻を迎える必要があったのだろうか……」とご自分が情けなく、遂には涙ぐんでしまわれました。 命こそ絶ゆとも絶えめ定めなき 世の常ならぬ仲の契りを (訳)命は絶えることがあっても、決して変ることのない二人の仲の契りよ…… 優美なお姿でお出かけになられる源氏の君を、紫上は穏やかにお見送りなさいました。けれども内心は、将来を不安にお思いになり、夜が更けるまで起きておられました。 女房たちがいろいろ悪口を言いますので、紫上は、 「あの方には女性が大勢おいでになりますのに、華やかな身分の高い方がお側にいないのを物足りなくお思いでした。今こうして内親王がお輿入れなさったのは、誠に結構なことでございましょう……」と仰いました。 昔、源氏の君が須磨に去られて、独り寝の寂しい夜を過ごした日々を思い出して、「あの頃は、例え遠く離れても、同じこの世に生きていられれば……と言い聞かせていました。今はご一緒にいられることだけでも幸せと思わなければ……」と思い直しなさいました。風が吹いて夜が冷たく感じられ、しみじみ哀れを感じさせるようでした。 その夜、源氏の君の御夢の中に紫上が現れましたので、ふと目を覚まされました。何か胸騒ぎがしましたので、夜も明けぬうちに急いでお戻りになりました。  雪明かりで辺りがほんのりとしていました。御格子戸を叩きましたのに、女房たちはわざと空寝して、ややお待たせしてから中にお入れしました。 雪明かりで辺りがほんのりとしていました。御格子戸を叩きましたのに、女房たちはわざと空寝して、ややお待たせしてから中にお入れしました。御身がすっかり冷えたまま、紫上の部屋の御衾を引き開けなさいますと、紫上は涙に濡れた単衣の袖を引き隠し素直で優しい素振りをなさいました。源氏の君はしみじみ愛しくお思いになりました。 今朝はこちらでお目覚めになり、 女三宮には御文をお届けになりました。 姫宮からのお返事には、 儚(はかな)くて 上の空にぞ消えぬべき 風の漂う春の淡雪 (訳)貴方がいないと、うわの空で、儚く消える春の淡雪のようです…… その筆跡はあまりにも幼稚ですので、源氏の君は、 「軽々しく他人に見せられない。まぁ、可愛らしいとするか……」とご覧になりました。 朱雀院は女御たちと 悲しいお別れをなさいまして、その月のうちに西山の御寺にお移りになりました。尚侍(ないしのかみ)(朧月夜)は尼になろうとお考えでしたが、院は、 「競って出家をするのはやめるように……」と説得をなさいました。 源氏の君にとって、この朧月夜は愛しいまま別れた忘れがたい姫君ですので、院が出家された今こそ、もう一度お逢いして御心の内をお伝えしたいとお思いでした。 紫上には「常陸(ひたち)の宮が患っているようなので、お見舞いに参ります」と嘘をつきなさいました。紫上は妙だ……とお思いになりましたが、女三宮が六条院においでになって以来、少し隔て心がついたのでしょうか。ただ素知らぬ振りをなさいました。 宵が過ぎるのを待って、粗末な網代車で忍んでお出かけになりました。朧月夜は源氏の君のお渡りに大層驚かれましたが、熱い想いを  一途に訴えなさいますので、いつまでも強い気持でもいられず、遂にはお逢いになりました。 一途に訴えなさいますので、いつまでも強い気持でもいられず、遂にはお逢いになりました。廂の間にお入りになりますと、御襖は固く錠めてありました。源氏の君は、 「この隔てをこのままでいられようか……」と御襖を引き動かし、 年月を中に隔てて逢坂の さも堰き難く落つる涙か (源氏の君) (訳)長い年月を経てやっとお逢いできたのに、この隔てには涙が落ちます 涙のみ堰き止め難き清水にて ゆき逢う道は早く絶えにき (朧月夜) (訳)涙が堰き止めがたい清水のように流れます。逢瀬の道は 昔に絶えてしまいましたのに… 朧月夜はご自分のせいで源氏の君が須磨に流され、世間の非難を受けた事を思い出しますと、すっかり気弱になられ、いつまでも拒むこともできずに…… 姫君は昔のままに若々しく、とても魅力的でした。深く想い乱れるご様子に、源氏の君は初めて逢った時よりも、強く心奪われてしまいました。 「昔、藤の宴でお逢いしたのは、たしか今頃だった。あれからどれほど長い年月が過ぎたことか……」と、妻戸を押し開けますと、外には見事な藤の花が咲いていました。 「美しい……この花影をどうして離れることができようか……」とお帰りを躊躇って、咲き匂っている藤の花を一枝折らせて、 沈みしも忘れぬものをこりずまに 身を投げつべき 宿の藤池 (訳)沈んでいた須磨も忘れないが、また懲りもせず、この家の藤の咲く淵に身を投げてしまいたいものです…… 朧月夜の姫君にとっても、藤の花は慕わしく思われるのでしょう。今はすっかり心許して、またの逢瀬をお約束なさいましたので、源氏の君はようやくご退出なさいました。 源氏の君は大層忍んで六条院にお帰りになりました。その寝乱れた髪をご覧になり、紫上はすっかりお分かりになりましたのに、ただ気づかぬ振りをなさいました。源氏の君はその心遣いを、いじらしくお思いになりましたが 、紫の上が、 「昔の恋を、今さら蒸し返しなさいますとは……」と涙ぐんでしまわれましたので、大層いとおしくなれ、永遠に変わらぬ二人の愛を誓って、心深くお慰めなさいました。 夏になりました。東宮の女御(明石の姫君)はご気分がすぐれず、どうやらご懐妊のご様子です。帝からようやく御暇が許されましたので、六条院にご退出なさいました。 寝殿の東側にお部屋を設けてお入りになりました。明石の上がお側に付き添って、六条院で娘のお世話をなさるお姿は、誠に理想的な運勢に見えました。 この女御は、実の母君よりも親しい方として、紫上を頼りになさっていましたので、紫上も細々とお世話をなさいました。紫上が、 「女御にお逢いするついでに、姫宮(女三宮)にもご挨拶申し上げましょう。お近づきになれましたら、私も気が晴れるでしょうから……」と申しなさいますと、 源氏の君は、 「それこそ望みどおりのお付き合いというもの。お二人が仲良くお暮らしになってほしいものです……」とお応えになりました。 紫上は姫宮にお逢いになりました。ただ子供っぽいばかりに見えますので、母親のように優しくお話しなさいました。姫宮のお気に召すようにと、お人形遊びの事などを申し上げますと、姫宮も「本当に優しく美しい方……」と子供心にすっかり打ち解けなさいました。 世間でも「これからは、紫上へのご寵愛も少しは劣るだろう……」と噂しておりましたが、今までよりも一層深い愛情が勝る様子でございました。 紫上は気品があり、全てに立派にお心遣いをなさいまして、長い年月連れ添った今も、眩いほどの美しさと優雅さとを備え持っておられます。この頃、何か哀しそうなご様子が漏れ見えますのに、何事もないような素振りをなさいますので、源氏の君は、 「何と素晴らしい方か……」と愛しく思わずにいられませんでした。 それなのに……今夜は、あの忍びの逢瀬に、実にどうしようもなくお出かけになりました。誠にけしからぬ事と反省なさりながら、朧月夜を想う御心は、どうすることもできないようでした。 神無月になり、源氏の君の四十歳の御賀のため、紫上は嵯峨野の御堂で薬師仏のご供養をなさいました。二十三日を御精進落としの日と定め、二条院でその宴が催されました。源氏の君は盛大になることを禁じなさいましたが、それでも御殿や調度品などが見事に設えられました。 寝殿には螺鈿の椅子がおかれ、東西の対に殿上人などの饗宴の席が設けられました。御殿の西の間にご衣装の机が並べられ、夏冬の御衣装や夜具などが置かれ、紫の綾織の覆いが掛けてありました。御前に置物の見事な机が二脚、背後の御屏風には美しい四季の絵が描かれておりました。御方々も然るべき事を分担して、進んでお仕えなさいまして、誠に豪華な素晴らしい祝宴となりました。 日が暮れる頃、舞楽が奏され「万歳楽」が舞われました。舞い終わる頃に権中納言(夕霧)と衛門の督(太政大臣の息子)が庭に下りて、美しい紅葉の蔭で「入綾」を舞われました。源氏の君は、昔、朱雀院の行幸で頭中将(とうのちゅうじょう)と舞った「青海波(せいがいは)」を思い出されて、今なお、その息子同士が、負けずに後を継いで競っておられる様子に、 「昔から並び合う両家の間柄なのだ……」と感慨深くおられました。 夜になり、管弦の遊びが始まりました。朱雀院がお譲りになった琵琶や、帝からの箏の琴など、昔を思わせる音色のままに合奏をなさいますと、しみじみと思い返されることが多くございました。源氏の君は、 「亡き藤壷の宮が生きておられましたら……」と悲しくお思いになり、帝も母宮がおられないことを、しみじみ心淋しくお思いでございました。 年が改まり、東宮の女御(明石の姫君)の出産が近づきましたので、御修法(みずほう)(祈祷)を絶え間なくさせなさいました。源氏の君は、昔、葵の上のご出産の折に、不吉な体験をなさいましたので、この女御が小さいお年頃であることを、大層心配なさいました。 あの大尼君(明石入道の妻)は、このご出産を喜び、度々参上なさいまして、源氏の君が明石の浦においでになった頃の様子や、都へ戻られた後に姫君がお生まれになった幸運などを、涙ながらにお聞かせ申し上げました。  東宮の女御は、 東宮の女御は、「私は栄華を極めるような身分ではないのに、紫上の御陰でここまで立派に育てられたのか……」と今はすっかりお分かりになり、袖を濡らしなさいました。 三月の十日過ぎ、無事に男御子(みこ)がお生まれになりました。特にお苦しみになることもなく、望み通りの男御子のご誕生に源氏の君も大層お喜びになりました。 紫上が白い装束をお召しになって、まるで母親のように若宮をお抱きになるご様子は、眩いほどに素晴らしいものでした。 七日の夜、内裏で御産養の儀式が、この世に例のないほど、盛大に優雅に催されたのでございました。 一方、明石の浦では、入道がこの話を伝え聞いて、大層喜びなさいまして、 「今はこの世から心安らかな気持ちで、離れていくことができよう……」と、人跡絶えた山奥に入ることをお決めになりました。最後に心情を書き綴り、明石の上にお送りになりました。 (入道の手紙) 人伝てに承りますと、姫君は東宮に入内(じゅだい)なさいまして男宮ご誕生とのこと、心から お喜び申し上げます。私自身、取るに足らない山伏の身で、今更この世で栄華を願ってはおりませんが、ただ六時の勤行には貴女の幸福だけを祈ってまいりました。 貴女が生まれる年の二月の夜、夢に、 『自分が捧げ持つ須弥山の左右から、月と日の光が同時にさし出して、世を照らしました。自分は小舟に乗り、西の方へ漕いでいく……』と見ました。 夢から覚めて、力及ばぬ身に思案余って、田舎に下り明石の浦に長くおりましたが、ずっと貴女に期待をかけておりました。国母となり御願が叶いましたなら、住吉の御社にお参りをなさい。今は阿弥陀の来迎を待って、私は勤行のため奥山に入山いたします。例え私の寿命が尽きるとも、決して心配なさいますな。極楽に行き着けましたなら、きっと再びお逢いできましょう。 (住吉の御社に立てた願文を文箱に入れ、これに添えてありました) 明石入道は、長年の勤行の間に掻き鳴らした御琴や琵琶を少しお弾きになってから、御仏にお別れを申されまして、遥かな山の雲霞の中に入られたのでございました。 明石の上は灯火を引き寄せて、この手紙をご覧になり涙を流されました。父入道に、このまま二度と逢えずに終わってしまうのか……と、胸が潰れる思いがなさいました。 「偏屈者で、私を不幸にしたと恨んだこともありましたが、高い理想をお持ちだったのか……」と、今やっとお分かりになったようです。 更に、尼君へのお手紙には、 「草の庵を出て深山に入ります。この身は熊や狼に施しましょう。貴女は望みどおりの御代になるのを見届けなさい。極楽浄土でまた逢えましょう 」とありました。尼君は涙を抑えて、 「貴方の御陰で身に余る幸運をいただきました。再び逢うことなく、一生の別れとなってしまったのが何よりも悲しい……」と、一晩中お二人はしみじみ語り合って、夜を明かしなさいました。 翌日、明石の上は東宮の女御の御前に参上なさって、父入道の文箱の事をお聞かせ申し上げました。 「この願文はお側にお置きになって、然るべき機会に、住吉に参詣して御願をお果たし下さいますように……。私など遠慮されるべき身分ゆえ、こうまでして頂けるとは思いませんでしたが、紫上の御心深いご親切のもとに、今では将来も安心できる気持でおります」と申し上げますと、女御は大層感動なさって、涙ぐんで聞いておられました。 源氏の君がおいでになりました。先程の文箱がそのままに置かれていましたので、 「何の箱ですか」とお尋ねになりました。明石の上は、 「明石の岩屋から内々に祈祷した巻々でございます。まだ願解きをしてないのがございましたのを、大殿にもご覧頂いた方がよいかと入道が送ってきたのですが、今は開けることもないでしょう」と申し上げますと、 源氏の君は、 「長年の勤行でどれほどの功徳を積み重ねなさったことだろう。是非逢いたいものだが……」と仰いました。 「今は鳥の声さえ聞こえない奥山に入ったと聞いております」 「ではその遺言なのですね……尼君にはどんなに悲しみの深い事でしょう」と涙ぐみなさいました。更に、 「貴女は今は少し道理がお分かりになったのですから、紫上のご好意をいい加減に思いなさいますな。血の繋がらない他人に情をかけ、深い好意をよせてくれるのは、並大抵のことではありません。お二人で心合わせて、この姫君のご後見をなさって下さい」と仰せになりまして、対の屋へお渡りになりました。 夕霧は姫宮(女三宮)のことがとても気になっておりました。六条院に御用のある時には自ら参上して、そのご様子を伺いなさいました。姫宮は大層幼く、一日中子供じみた遊びや戯れ事に熱中のご様子でしたが、源氏の君は大目に見て、叱る等はなさいませんでした。ただ将来を考えて、その態度や振舞いだけは、充分にお教えになりました。 衛門(えもん)の督(かみ)(太政大臣の息子)は、院が大切になさったこの姫宮が、こうして源氏の君にご降嫁なさいましたことを、とても残念に思われ、「源氏の君がいつの日か出家なさった折には……私が……」と今も諦めきれないまま、姫宮を想い続けておりました。  三月、空が麗らかに晴れた日、大殿は所在なくおられましたので、丑寅の町で蹴鞠(けまり)を楽しんでおられた夕霧を呼び寄せなさいました。兵部卿宮や衛門の督などもご一緒に参上なさいました。 三月、空が麗らかに晴れた日、大殿は所在なくおられましたので、丑寅の町で蹴鞠(けまり)を楽しんでおられた夕霧を呼び寄せなさいました。兵部卿宮や衛門の督などもご一緒に参上なさいました。桜が舞い散る木陰で、蹴鞠に興じる若い公達のお姿が楽しげで美しく見えますので、女房たちも御簾の蔭に集まって来ました。 その時、小さな可愛い唐猫が急に御簾の端から飛び出しました。猫につけた綱がひっかかり、逃げようと引っ張るうちに、御簾の端が引き開けられました。少し奥まった所に、紅梅襲(こうばいがさね)の袿(うちぎ)姿で立っていらっしゃる姫宮のお姿が見えました。衛門の督はもう胸がいっぱいになり、その愛らしいお姿が心に焼きついて忘れられなくなりました。 蹴鞠の後、皆は酒宴をなさいましたが、衛門の督はただぼんやりしておりました。思いがけず御簾の隙間から見えた姫宮の姿を思い出し、お側に近づき難い身分の差を思い知らされ、ただ胸塞がる思いがして、 「どうしたらこの熱い想いを、姫宮にお知らせできようか……」と、小侍従(こじじゅう)(女房)のもとに手紙をおやりになりました。 よそに見て 折らぬ嘆きはしげれども 名残り恋しき花の夕影 (訳)よそから見るだけで、手折ることのできない悲しみは深いけれど、 夕影に見た花の美しさは、今も恋しく想われます 小侍従は先日の出来事を知りませんので、ただの恋患いだろうと、他の女房たちがいない時に、この手紙を姫宮にお見せしました。姫宮は、 「あの時、御簾の端にいた不注意を、源氏の君に知られたら、どんなにお叱りになるだろう……」とお思いになり、若い公達にお姿を見られてしまったことが一大事とは、少しも思っていない……何とも幼いご様子でした。 小侍従はこっそりと返事を書きました。 今更に 色にないでそ山桜 およばぬ枝に心かけきと (訳)今更、お顔の色に出しなさいますな。手の届かない桜の枝に、 想いを寄せるのは無駄なこと…… ( 終 ) |
若菜(わかな)下 ー第三十五帖 六条院の賭弓の集いには、大勢の人々が参上なさいました。衛門(えもん)の督(かみ)は気が進まない様子でしたが、女三宮がおられる辺りの桜を見れば、この苦しい想いが慰められることもあろうか……とお出かけになりました。 弓の優れた人々が凛々しく競っ合っていますのに、ただ物思いに耽っては、 「六条の大殿に降嫁したあの姫宮を、想い続けてよいものか。……大それたことだ。ただ人から非難されるような振る舞いだけはするま  い」などと思い悩んだ末に、「せめてあの日の唐猫でも手に入れて、寂しい独り身の慰めに懐かせてみよう……」と思いつかれました。 い」などと思い悩んだ末に、「せめてあの日の唐猫でも手に入れて、寂しい独り身の慰めに懐かせてみよう……」と思いつかれました。弘徽殿の女御のところにお立ち寄りになり、 「六条院の姫宮(女三宮)のところにいる唐猫が、とても可愛らしい……」とお話ししましたので、早速、女御はその唐猫をご所望なさいました。衛門の督はその唐猫が懐かないのを口実に、自分の手元に引き取り、昼も夜も身近において可愛がりました。やがて猫はとてもよく馴れて、甘えるようになりました。 ある日、衛門の督が端近くにおりますと、その唐猫が「ねょう、ねょう」と愛らしく鳴きますので「寝よう、寝ようと泣くのか……」と、思わず苦笑なさいました。 恋ひわぶる人のかたみと手ならせば なれよ何とて鳴く音なるらむ (訳)恋しい人の形見と思いながら、手懐かせると、どうしてそんな鳴き声をするのか 愛しい姫宮のことを想いながら、その猫を懐に入れて、物思いに耽ってお過ごしになりました。 その頃、あの蛍兵部卿はまだ独身で、想いを寄せた方々は皆、叶わず、世間の物笑いになるのかと心配して、式部卿の大宮に漏らしましたところ、大宮は、あの鬚黒の大将の愛娘・真木柱の姫君との仲をお認めになりました。しかしもともと浮気癖のある宮は、この姫君を物足りなくお思いになり、今も亡き北の方を恋しくお想いのようで、真木柱の所にお通いの様子も大層億劫そうに見えました。父・鬚黒大将も姫君を可哀想に思いましたが、そのような夫婦仲のまま、時が過ぎてゆきました。 年月が流れ、冷泉帝が即位なさってから十八年が経ちましたのに、帝はご自分のご出生について大層思い悩まれ、ある日突然に、帝の御位を退いてしまわれました。 源氏の君は退位されたこの帝に後継ぎがないので、子孫にまで皇位を伝えることが出来なかった……と残念にお思いになりました。 東宮の女御(明石の姫君)には御子が大勢いて、ますますの御寵愛に並ぶ者がないほどですが、世間の人々は、引き続いて源氏の血筋が皇后になられることを、不満に思っておりました。 六条院の姫宮(女三宮)は、帝が大層気遣いをなさいましたので、世間からも広く重んじられておられました。年月が経つにつれ、源氏の君とのご夫婦仲も睦まじくなられましたので、紫上は「もうこの世はこれまで……」と度々、出家を望まれました。 けれども源氏の君は、 「何と辛いことを……。私自身が出家を望んでいながら、後に残す貴女のことが気がかりなばかりに、この世に留まっているのです。 どうぞその事は、私が出家した後にお考えください……」と聞き入れなさいませんでした。 秋になりました。源氏の君が、あの明石入道の御文箱を開けてご覧になりますと、中には子孫の永遠の繁栄を祈願した数々の願文が入っていました。 「あのような山伏で、よくぞこのような御願を……きっと前世の因縁で仮に身を変えた修行者だったのだろう……」と感慨深くお思いになり、住吉参詣に出立なさいました。 一行は上達部をはじめ、舞人や御神楽まで、優れた者ばかりを数多くお選びになり、御馬や鞍まで飾り揃えた見事さは、この世にまたとないほど素晴らしくございました。 女御と紫上は同じ御車に、次の御車には、明石の上と尼君がお乗りでございました。それに続くお供の車は、紫上の御方のが五台、女御方が五台、明石のご一族のが三台と、いずれも目も眩むほど美しく飾り立てておりました。 住吉の御社に着きましたので、東遊び(神楽)が催されました。玉垣に這う葛(かずら)も色付いて、秋の風情を感じられる頃、松風に吹き立てる笛や琴の音が、波風に響き合って優雅で一層素晴らしく聞こえました。源氏の君は昔のことを思い出されましたが、その当時の事を語り合える人も今は無く、しみじみと感慨深く思われました。 一行は一晩中神楽を奏して夜を明かされました。 紫上はいつも邸内におられ、御門から外を見物をなさることもなく、まして都より外にお出かけなさった経験さえありませんので、総てのものが珍しく、興味深くお感じになりました。ご自分の人生を振り返り、 「長い年月、源氏の君が大事にして下さる御陰で、その愛情は他の人に負けることはありませんでしたが、余りに年を取りすぎたら、いつの日かそれも衰えてしまいましょう。そうなる前に、自らこの世を捨てて、出家をしたい……」と一層強く思っておいでになりました。やはり女三宮をお迎えしてから、源氏の君のお渡りがだんだんと少なくなってきましたので「無理もないことなのか……」と悲しくお思いになりました。 源氏の君のおられない寂しい夜には、春宮のすぐ下の女一宮を手元にお引き取りになって、その姫宮のお世話をして、気を紛らわせておられたのでございました。 朱雀院は最期が近づいた心地がなさいまして、すっかり心細くなられました。 源氏の君は何をして、院をお慰め申そうかとお考えになり、来年迎えられる五十の御賀の祝を、二月十日頃に行うことをお決めになりました。院は音楽にご造詣深くおられましたので、舞人や楽人などを特別に選りだして、心尽くしてその祝宴の準備をおさせになりました。 姫宮(女三宮)は以前から御琴をお習いでしたので、この機会に是非、父院にお聞かせ申そうと、源氏の君が朝から晩まで熱心にお教えなさいました。やがて習得なさるにつれて、姫宮は大層上手になられました。御年二十一ほどになられましたが、まだとても幼げで未熟な感じがしました。父院に久しくお逢いしていませんでしたので、ご立派に成人なさった……とご覧いただけるように、大層努力なさったのでございます。 正月二十日頃、空模様も麗らかに晴れ、風が暖かく吹いていました。御前の梅も盛りになりました頃、六条院で女楽が催されました。廂の中の御障子を取り外し、御几帳を境にした中の間に、院の御座所を設けました。明石の御方に琵琶、紫上に和琴、女御の君に箏の琴、そして姫宮にはいつもの慣れた御琴を差し上げなさいました。 調弦のために夕霧をお呼びになりますと、香の染みた鮮やかな直衣姿で、大層緊張して参上なさいました。各々の調弦が終わり、御方々が美しい音色で合奏なさいました。 姫宮は誰よりも小さく可愛らしげで、桜の細長をお召しになり、二月の青柳が垂れ初めたように弱々しく見えました。 女御の君は紅梅襲の御召物で雰囲気が奥ゆかしく、咲きこぼれる藤の花のようでした。 明石の御方は他の御方々に圧倒される気配もなく、萌黄の小袿は五月を待つ花橘の薫りを思わせ、その琵琶の音色は澄みきって美しく聞こえました。 紫の上は葡萄染の色濃い小袿をお召しになり、和琴を魅力的な爪弾きで華やかにお弾きになりました。源氏の君はやはり紫上こそ、またとない方とお思いになりました。 姫宮の琴は未熟ではありますものの、他の音色によく響き合って、朱雀院も扇を打ち鳴らして一緒にご唱歌なさいました。月が遅い頃なので、灯籠に明かりを灯して、優雅な女楽は夜遅くまで続きました。 翌日、源氏の君は対へお渡りになりました。紫上に、 「姫宮の御琴は大層上手になられたものだ。どのようにお聞きになりましたか」 「この上なく上手におなりです。あのように熱心にお教えなさったのですから……」とお答えなさいました。 紫上は今年三十七歳(厄年)におなりでございました。世間では『すべてに備わってお気遣いをなさる方は、長生きしない……』とよく言われますので、源氏の君は何か不吉にお思いになって、然るべきご祈祷などを、例年より特別にさせなさいました。 源氏の君はご自分の半生をしみじみと振り返り、 「私は大層恵まれた育ち方をして、世の評判を手中にしてきましたが、愛する人々に先立たれ、取り残された晩年になっても心満たされず、悲しく思う事が多くございます。 貴女には、須磨流離の他には、心痛めるようなことはあるまいと思っています。 后としての気苦労もあり、思いがけず姫宮(女三宮)がお輿入れなさいましたのは、何やら辛くお思いでしょうが、それでも一層勝る愛情をお受けになったことをお分かりいただけたはず……、人並み以上のご運勢とお分かりでしょう……」 「仰るように、この身には過ぎた運命と世間には見えましょうが、心には物思いばかりがつきまとい、もうとても行く先長くない心地がいたします。以前にも申し上げました通り、何とか出家をお許しいただきたく……」 「とんでもない。そうなれば、後に残された私に何の生き甲斐があるだろう。今は朝に晩に顔を合わせるだけで嬉しく、……貴女を心から深く愛しているのです。どうか最後まで私を見届けてください……」と強く申しなさいますので、紫上は大層胸が痛んで、ただ涙ぐんでいらっしゃいました。そのお姿をご覧になりまして、源氏の君はなお愛しくお思いになり、心深くお慰めなさいました。更に、 「若い頃、葵の上(夕霧の母)を妻に持ちましたのに、夫婦仲が好ましくなく、心打ち解けぬまま亡くなってしまいましたのが、今も残念でなりません。 秋好中宮の母君(六条御息所)は、嗜み深く優雅な方でしたが、朝夕睦まじく語り合うにはとても緊張し、気詰まりな性格の方でした。そのまま疎遠になりましたことを、深く怨まれたのは辛いことでした。罪滅ぼしに、今はその娘・中宮をお世話していますのを、あの世から見て、御息所は思い直して下さったでしょうか……。 明石の上については、身分が低いと軽く見ていましたが、従順ながらしっかりした人です。しかし何よりも貴女が、女御の御為に心尽くしておられるご様子が、誠に素晴らしく思われます……」と心深く微笑みなさいまして、 「さて、姫宮に、琴をとても上手にお弾きになった御祝を申し上げて来よう……」とお渡りになりました。 紫上は、いつものように、源氏の君のおられない夜は遅くまで起きていて、女房達に物語など読ませてお過ごしになりました。夜も更けてからお寝みになりましたが、その明け方、胸を病み大層お苦しみになりました。女房が「大殿にお知らせ申しましょう」と言うのも制しなさって、苦しいのを我慢して夜を明かしなさいました。 女御の御方からこれをお聞きになって、源氏の君が急いでお帰りになりますと、紫上はお身体に熱があり、とても苦しそうに臥せておられました。一日中側に付き添って介抱なさいましたが、我慢できないほどお苦しみになりますので、御祈祷などを限りなくさせなさいました。 このような状態のまま二月も過ぎました。源氏の君は大層お嘆きになり、紫上がお育ちになりました二条院へ、紫上をお移しになりました。冷泉院も大層悲しまれ、大将の君(夕霧)も心尽くしてお見舞いなさいました。 紫上は、少し意識のはっきりしている時に、 「何度もお願いしていますのに、出家のお許しもなく、ただ情けない……」とお恨みになりました。とても頼りなさそうに弱々しくなられ、もうこれきりと見えますので、御修法の阿闍梨(あざり)(高僧)たちも「何ともお労(いたわ)しい……」と祈祷申し上げておりました。 あの衛門の督(柏木)は中納言になられました。世間の御信任も大層厚く、ご自分の声望が高まるにつけても、女三宮を慕う心は募るばかりでした。思い叶わぬ悲しさから、せめて心の慰めになろうかと、その姉宮(女二宮)をご降嫁いただきました。人に見咎められない程度にお世話なさいましたけれども、やはり心慰められることはありませんでした。 もろかずら落ち葉を何に拾ひけん 名はむつましきかざしなれども (訳)二つの鬘(かずら)の落ち葉の方を、どうして(妻として)拾ってしまったのか 名前は睦まじい簪だけれども…… 六条院では、紫上の看病のために、源氏の君がずっと留守にしておられましたので、人目が少なくひっそりとしていました。その時を見計らって、衛門の督が度々、小侍従(女三宮に仕える女房)を訪ねて来ました。 「このように寿命も縮むほどに慕っていることを、姫宮にお伝えしたいので、何とかして逢わせて欲しい。その姉宮(落葉の宮)を頂戴したというのに、心慰められることもなく……」と溜息を漏らしました。小侍従は腹立たしく思いながらも、源氏の君がおいでにならない夜が続き、姫宮も心細く過ごしておられますので、遂に手引きを引き受けてしまいました。 御禊の前日、人々はそれぞれに忙しく御前がひっそりとして人少なの頃、小侍従だけが姫宮のお側近くに仕えていました。 「今こそよい機会だ。せめて物越しに逢うのならば……」と、御帳台の東の御座所に、衛門の督を導き入れました。 姫宮はまだ無心にお寝みになっていましたが、近くに男の気配を感じ、源氏の君がおいでなのか……と思いました。男は畏まった態度 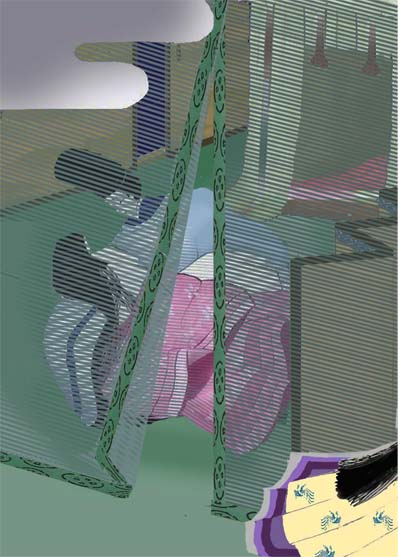 で、姫宮を浜床の下に抱き下ろしました。姫宮が目を開きますと源氏の君ではありません。恐ろしくなり女房を呼びましたが、誰も近くに控えていないようです。その怯えるお姿がとても可憐に見えますので、衛門の督は懸命に抑えていた分別を、今は、すっかり失って…… で、姫宮を浜床の下に抱き下ろしました。姫宮が目を開きますと源氏の君ではありません。恐ろしくなり女房を呼びましたが、誰も近くに控えていないようです。その怯えるお姿がとても可憐に見えますので、衛門の督は懸命に抑えていた分別を、今は、すっかり失って……「姫宮をお連れして、どこかにお隠し申し上げ、自分もこの世を捨てて姿を隠してしまいたい……」 その夜、うとうとした夢の中にあの唐猫が可愛く鳴きました。 衛門の督は、 「やはり逃れられない宿縁があったのだ……」と思いました。 姫宮はただ途方にくれ、悲しく心細くお思いになって、まるで子供のようにお泣きになりました。衛門の督は、そのお姿を愛しく拝見して、御袖を涙で濡らすばかりでした。 起きてゆく空も知られぬ明けぐれに いづくの露のかかる袖なり (衛門の督) (訳)起きても帰る行く先も分からない明け暮れに、 どこから露がかかって袖が濡れるのでしょう…… 明けぐれの空に憂き身は消えななむ 夢なりけりと見てもやむべく (女三宮) (訳)明けぐれの空にこの身は消えてしまいたいもの 夢であった……と済まされるように…… 衛門の督は姉宮(妻)のところには帰らずに、大殿へおいでになりました。横になられましたが眠る事も出来ずに、あの夢の中の猫のことを思い出していました。 「それにしても、大変な過ちを犯したものだ。源氏の君の御妻を……この世に生きていくことさえ出来なくなってしまった……」と、恐ろしくて身もすくむ思いでした。 悔しくぞ摘み犯しける葵草 神の許せるかざしならぬに (訳)悔しい事に罪を犯してしまったことよ、神が許した仲ではないのに…… 姫宮がご気分がすぐれないとお聞きになって、源氏の君がお渡りになりました。特に苦しそうな様子もなく、ただとても恥ずかしがってお顔を合わされませんので、 「長く留守にしたことを、そんなに恨んでおいでなのか……」とお慰めになりました。 姫宮には、源氏の君が忍びの出来事にお気づきでないことがかえって辛く、つい涙が溢れるのでした。 源氏の君はすぐにお帰りになることもできずに、姫宮のところにおられますと、 「紫上が息を引き取られました……」と使者が参上しました。 源氏の君は突然のことに御心が真っ暗になり、急いで二条院にお帰りになりました。邸内には僧たちが立ち騒ぎ、誠に不吉な雰囲気に包まれておりました。 「まさか……臨終の時さえ、逢わずに逝ってしまったのか……」と大層取り乱し、「もう最期なのか……。そうは言っても、これは物怪(もののけ)のしたこと。不動尊の御誓があるのだから、何とかもうしばらくの間でも、この世にお引き留め申して下さい……」と、黒煙を立てて一心に加持祈祷をなさいました。 すると今まで全く現れなかった物怪が紫上の傍らにいる童女に乗り移って、大声でわめき立てました。 「他の人は皆立ち去りなさい。源氏の君ただお一人にお話し申したいことがあります」と、髪を振り乱して泣く物の怪は、昔、源氏の君がご覧になった六条御息所の死霊のようでした。源氏の君はこの童女の手を捉えて、 「本当に貴女ですか。はっきり名乗ってください……」と責めますと、童女はひどく泣いて、御息所の声で、 「私はすっかり変わり果てましたが、貴方は昔のままの酷い方です。……先日、紫上に『御息所は気詰まりな性格の女……』と、私のことを悪く仰いましたね。それが恨めしく思われます。この紫上が憎くて取り憑いた訳ではありません。ただ神仏のご加護が強くて、源氏の君のご身辺に近づく事ができなかったのです……」と申しました。 源氏の君は何とか物の怪を封じ込めて、紫上を別の部屋にお移し申しました。 そのうちに……紫上にはだんだんと生き返る気配が見えてきましたので、恐ろしくも嬉しくお思いになって、いくつもの御修法をすべて祈祷させなさいました。 紫上がずっとご出家を切望なさっていましたので、五戒だけを受けさせ、源氏の君はずっとお側に付き添って、 「どのようなことをしてでも、この紫上をお救いし、この世に引き留めておこう……」と仏に念じなさいました。そのお振る舞いは大層ご立派で凛々しうございました。  五月になり、湯薬を召し上がったせいか、紫上は少し回復なさいました。 五月になり、湯薬を召し上がったせいか、紫上は少し回復なさいました。御庭の池には涼しげに蓮の花が咲いていました。青々とした葉の上に、露が玉のように輝いているのをご覧になり、 消え止まる ほどやは経べきたまさかに 蓮の露のかかるばかりを (紫 上) (訳)露が消え残っている間だけ でも生きられましょうか…… 蓮の露のように儚いほどの命です から…… 契り置かむ この世ならでも蓮の葉に玉ゐる露の心隔つ (源氏の君) (訳)お約束しましょう。この世ばかりでなく来世にも、蓮の葉に 玉と置く露のように心の隔てなさいますな…… 源氏の君は六条院にほとんどお渡りになりませんでした。 姫宮はあの忌まわしい出来事を大層お嘆きになり、先月からは食べ物も召し上がらずに、ひどく青ざめて窶(やつ)れてしまわれました。 姫宮がお苦しみと聞いて、源氏の君がお渡りになりました。ちょうど姫宮は御髪を洗って爽やかにしていらっしゃいましたので、青白いけれど可愛らしげに見えました。 けれども良心の呵責に苛まれ、お逢いになるのも気が引けるのでしょうか。源氏の君の仰る言葉にお返事もなさらないので、長いこと逢わずにいたことを、そんなに辛くお思いなのか……と、優しくお慰めなさいました。年輩の女房が、 「実は、ご懐妊のご様子でございます……」と申し上げますと、源氏の君は、 「妙だなぁ……今頃ご懐妊とは……」とだけ仰って、まだ年端(としは)のいかない姫君をむしろおいたわしく拝見なさいました。 衛門の督が苦しい胸のうちを書き綴り、大層忍んで姫宮にお届けになりました。人少なの頃を見計らって、小侍従がこっそりと姫宮にお見せしました。ちょうどそのお手紙を広げたところに、源氏の君が入って来られましたので、姫宮はうまく隠すこともできずに、御褥(しとね)の下に急いで差し挟みました。そして……すっかり忘れてしまいました。 源氏の君は御座所に横になられ、お話などなさいますうちに、日が暮れてしまいましたので、無情に帰るのも可哀想に思われて、その日はお泊まりになりました。 まだ朝の涼しい頃、昨夜なくした扇を探そうと、御座所の辺りにおいでになりますと、御褥の下から浅緑の手紙の端が見えていました。何気なく引き出してご覧になりますと、男の筆跡で細々と書いてありました。 「これは紛れもなく、衛門の督の……」 姫宮はまだ無心にお寝みでしたので、源氏の君はそのまま退出なさいました。 繰り返し御文を読み返しなさいますとそこには長年慕い続けていた姫宮に、想いを遂げたその心情が熱く書き綴られておりました。 「……それにしても……これから姫君をどのようにお扱いしたらよいものか。突然のご懐妊とは、まさかこのせいなのか。何と忌々(いまいま)しいことだ。誠に不愉快なことではあるが、顔色に出すべき事ではないし……」と大層思い悩まれました。 そして……昔の継母・藤壷中宮との逢瀬を思い出され、 「まさか故桐壺院(父院)も、実はご存知で、素知らぬ顔をしておられたのだろうか。それを思うと誠に恐ろしい。あってはならない過失だった……」とお思いになりました。 源氏の君がお帰りになりました後、小侍従が、 「昨日の手紙はどうされましたか。今朝、大殿がご覧になっていた手紙の色がとても似ていたようですが……」と申し上げますと、姫宮は「褥に挟んで、すっかり忘れていました……」と必死で捜しました。けれども見付かるはずもありません。 それからというもの、源氏の君のお渡りのない日が続きますのも、すべてご自分の過失とお分かりになり、姫宮は身の置き所のない気持がして大層お苦しみになりました。 一方、衛門の督の御心は一層募るばかりで、今一度姫宮に逢わせて欲しいと、女房に熱心に手引きを頼みました。小侍従が「源氏の君はすべてご存知です……」と話しますと、衛門の督は大層驚いて、身も凍りつくような心地がなさいました。 「長い年月、源氏の君は誰よりも親しく御心をかけて下さいましたのに……」 それからというもの、内裏へも参上なさいませんでした。 源氏の君は、今も朧月夜の姫君を心から慕っておられましたのに、姫君は遂に出家をしてしまわれました。誠に口惜しく、御文に、 海人の世をよそに聞かめや須磨の浦に 藻塩垂れしも誰れならなくに (訳)出家されたことを他人事と聞けましょうか 須磨の浦で涙に沈んでいたのは、誰ならぬ貴女のせいですから…… 様々な世の無常を思いますと、私をお見捨てになったかと悲しく……昔からの辛い契りは心浅くはなかったはずですのに……」等と、細々とお書きになりました。 朧月夜はこれが最後の御文と決め、心してお書きになりました。墨継ぎも美しく、 海人舟にいかがは思ひおくれけむ 明石の浦にいさりせし君 (訳)尼になった私にどうして遅れたのでしょう 明石の浦に海人のように暮らしていた貴方が…… 二条院におられる時にこの御文が届きましたので、今、朧月夜との仲が終わったとして、紫上にもそれをお見せになりまして、折々によせて情緒を語り合える人が、遂に出家をしてしまわれた……と、寂しくお思いになりました。出家のご準備にと、青鈍の尼衣を誂え、尼のお道具類などをも格別にお揃えになってお贈りになりました。 ずっと延期になっていた朱雀院の五十の御賀も、最近、女三宮がひどくお悩みのご様子で、再び延期になりました。ご懐妊の月数が重なるにつれ、大層辛そうになさいますので、それをご心配なさいました朱雀院は、女三宮に何か不都合でも起きたのか……と、お見舞いの御文をお書きになりました。 源氏の君は、 「姫宮の不義が父院のお耳に入るはずもありませんから、姫宮がお苦しみなのは、私の怠慢のせいだと思し召されるでしょう。年老いた私を嫌とお思いでしょうが、父院のご存命中は我慢をしてください。院のご寿命もそう長くはないのですから、今さら悪い噂をお聞かせして御心を乱すことのないように……来世の御成仏の妨げとなりましょう」とお話しなさいました。姫宮も涙がこぼれて、悲しみに沈んでしまわれました。源氏の君は硯を引き寄せ、仰るとおりの言葉を姫宮に書かせて、父院にお返事をさせなさいました。  十二月になりました。朱雀院の御賀もこれ以上延期することはできないと、十日過ぎに催すことを決めましたので、御邸中がその準備に大騒ぎをしておりました。源氏の君は、楽に優れた衛門の督が参加しないことを物足りなく感じられ、御前にお召しになりました。衛門の督は重病であるからとお断りなさいましたが、父大臣が強くお勧めになりましたので、苦しいながらも参上されました。 十二月になりました。朱雀院の御賀もこれ以上延期することはできないと、十日過ぎに催すことを決めましたので、御邸中がその準備に大騒ぎをしておりました。源氏の君は、楽に優れた衛門の督が参加しないことを物足りなく感じられ、御前にお召しになりました。衛門の督は重病であるからとお断りなさいましたが、父大臣が強くお勧めになりましたので、苦しいながらも参上されました。いつものように、お側近くに招き入れ、母屋の御簾は下ろしてお逢いになりました。衛門の督はひどく痩せ青白い顔をして、顔を上げることさえできずに控えておられました。 源氏の君は内心「姫宮との不義については、全く許すことは出来ない……」と大層お腹立ちでしたが、何事もなかったかのように平静を装って、 「院の御賀のため、わが子供たちに舞など習わせ始めたのだが、調子を合わせることは、貴方の他に誰にお願いできようか……」と仰いました。 衛門の督は大層嬉しく思うものの、内心では身の縮む思いがなさいました。青ざめた様子で、 「ここ幾月、病気に苦しんで臥せておりましたが、院の御賀には誰よりも深い敬意を表したいものです……」とお答え申しました。 御賀の試楽の日、東南の釣殿に続く廊を楽所に設えて、楽人三十人が「仙遊霞」という楽を奏しました。雪が僅かに散らつき、梅の花が美しく咲いていました。右の大殿の四郎の君、大将殿の三郎の君などは、まだとても幼いながら「万歳楽」を舞いました。一族の子供達が「太平楽」「喜春楽」などを舞い、可愛らしい孫の君達の深い才能に、年老いた上達部たちは皆、感涙を落とされました。源氏の君も、 「年をとると酔い泣きは止められないものだ。衛門の督が老い(ヽヽ)を笑っているようだが、老いとは誰もが逃れられないものなのだよ……」と、酔った振りをして皮肉を仰り、盃を繰り返し無理強いなさいました。衛門の督は大層気分が悪くなられ、胸が痛くなって、遂には我慢できずに、まだ宴も終わらないうちにお帰りになりました。 そして……そのまま重い病に臥せてしまわれました。 朱雀院の御賀は二十五日に催されました。衛門の督のご容態を気遣って、皆が嘆いておられる頃でしたが、今まで次々と延期されてきましたので、強いて催されたのでございます。 ( 終 ) 次の要約(5)へ進む |
| 要約 「源 氏 物 語」 発行 2006年1月吉日 製作 WAKOGENJI 文・挿絵 小川和子 古典「源氏物語」を読む会 無断の複製・転載をお断りします。 |