|
源氏の君がお亡くなりになりました後、あの輝きをお継ぎになる方が、大勢の御子孫の中にはおられません。御譲位された帝(冷泉)を源氏の上に奉るのは、誠に畏れ多いことでございます。
今上帝の三の宮(匂宮)と、六条院にて同じように育ちなさいました女三宮の若君(薫)、このお二人こそが、それぞれに美しいと評判でございますが、なるほど普通でない程のご器量ではありますけれど、眩いほどではおられないようです。
 ただ、世の常のように、素晴らしく高貴で雅美においでになるので、その様な御一族ゆえ、世間が思い込みとしてお扱い申し上げるご様子が、昔の源氏の君の御威光や有様よりやや勝っていらっしゃるゆえ、このうえなくご威勢があるのでございました。 ただ、世の常のように、素晴らしく高貴で雅美においでになるので、その様な御一族ゆえ、世間が思い込みとしてお扱い申し上げるご様子が、昔の源氏の君の御威光や有様よりやや勝っていらっしゃるゆえ、このうえなくご威勢があるのでございました。
三の宮(匂宮)は、紫上が生前、特に御心を尽くして可愛がりなさいました故に、今も二条院にお住まいでございます。春宮(一宮)は、帝・后が高貴な方としてお取り為しなさいまして、内裏にて大層大切にお世話申し上げ、この匂宮をも内裏にて生活なさるようにお計らいなさいましたが、三の宮ご自身は、やはり心安い古里(二条院)を住みやすくお思いでした。
元服をなさいまして、兵部卿の宮となられました。
今上の女一宮は、六条院の南町の東の対を、紫上の御設えなどを改めずにお住いになって、朝夕に紫上を恋しくお思いになりました。二宮も同じ六条院の寝殿を里下りの時などの御休み所になさいまして、内裏では梅壺をお部屋になさって、右の大臣殿(夕霧)の中姫君をお迎えしてお世話申し上げておられました。
二の宮は次の春宮候補として、世の評判も特に重々しく、人柄も健やかにおいでになりました。
大臣殿の御女(むすめ)(姫君)はとても大勢いらっしゃいました。大姫は春宮に入内なさって、競う相手もない様子で伺候しておられました。そして次々に「やはり皆、大君に続いてそのまま……
」と世間も思い、后の宮(明石中宮)もそう申しなさるのですが、この兵部卿の宮、ご自身はそうはお思いにならず、自分が望んだ縁談ではないので面白くない……とお思いのようでした。
大臣も「なにも……結婚はそのようにのみ、きちんとすることでは……」と、落ち着いていらっしゃいますが、もし匂宮にそのようなご意向があるのならば、お断りすることはない」という気持で、大層、大切にお世話をしておいでになりました。
六の君は、少し「我こそは……」と思い上がっておられる親王達・上達部たちの御心を、夢中にさせる種をお持ちのようでございました。
源氏の君の亡くなられました後、さまざまに六条院にお集まりになっていた御夫人方は、泣く泣く、終の住み家などに、皆、各々お移りになりました。花散里と申し上げる方は、二条院の東の院 をご遺産としてお受けになり、お移りになりました。入道の宮(女三の宮)は三条宮におられます。今后(明石中宮)は、内裏にのみ伺候しておられますので、六条院もなんとなく寂しく、人少なになりました。右の大臣(夕霧)は、
「他人事として、昔の例(ためし)を見聞きするにつけても、私が生きる限り、心尽くして造り上げた人の御邸が、残(なご)り無くうち捨てられ……人の世を無情と思えるのは、大層悲しく儚いこと、と思い知らされる。私が生涯、この六条院だけは荒廃させることなく、又、近くの大路なども、人の賑わいが見えるようにしたいものだ……」とお思いになり、そう仰って、その六条院の丑寅の町に、あの一条の宮(落葉の宮・故柏木の妻)をお移しなさいまして、三条殿(雲居雁邸)と、一夜毎に十五日ずつ、交互にきちんとお通いになったのでございました。
院(源氏)が二条院を造り磨き上げ、六条院の春の御殿として、世に評判であった玉の御殿も、
「ただお一人の将来のためであった」と見えて、明石の御方は、大勢の宮たちの御後見をしながら、お世話申し上げておいでになりました。
大臣殿(おおいとの) (夕霧)はどの方の御事をも、父院のお決めになった通り改変することなく、広い親心のようにお世話なさいまして、
「対の上(紫上)が、今も生きていらっしゃったならば、どれほど心を尽くしてお世話申し上げてご覧にいれたことか……。遂に、ほんの少しでも、私が好意を寄せていたことを、お分かり頂く折もなく逝ってしまわれた……」と、誠に残念に物足りなく思い出しておいでになりました。
天下の人々は院(源氏)を恋い慕い申し上げない者はなく、何事につけても、世の中はただ火を消したたように、何の張り合いもない……と、嘆かない折もありませんでした。まして、殿内の女房たちや、ご婦人方・宮たちは、更に申し上げるまでもなく、限りない悲しみは勿論のこととして、また、あの紫上のご様子を心に深く留め、総ての事につけて、悲しく思い出しておられました。春の桜の盛りは長くないことによって、かえってその想いも強くなるようです。
院が申し遺しなさいました通り、二品(にほん)の宮(女三宮)の若君(薫)を、冷泉院の帝は、特別に大切にお世話しておられました。后の宮(秋好中宮)には、親王などもおられず、心細く思われますので、嬉しい後見役として、正式に頼りに思い申し上げておられました。御元服なども、冷泉院にてさせなさいまして、十四になられ、二月に侍従になられました。その秋、右近の中将になられ、恩賜の加階などまで……どこか心細く思われてか、急ぎ加えてご成人させなさいました。
帝がお住まいの御殿の近くの対屋に、薫の部屋を設えて、冷泉院がご自身で監督なさって、若い女房・童・下仕えまで、優れた者を選び整えさせなさいました。帝や中宮(秋好)にお仕えする女房の中にから、器量がよく上品で感じがよい者を、皆、こちらにお移しなさいまして、御殿を気に入って住みよく、生活しやすいと思うようにとお気遣いなさいまして、この薫君を特別扱いなさっておいででございました。
院には、故致仕の大臣の女御(弘徽殿(こきでん))と申す方の御腹に、女(おんな)宮(みや)がただ一人いらっしゃいますが、この女宮を限りなく大切にお世話なさるご様子に劣らないほど、后の宮の薫に対するご寵愛が、年月と共に勝りなさいますので、人々は「どうして、それほどまでに……」と見ておりました。
母宮(女三宮)は、今はただ仏道の勤行のみを静かになさいまして、月毎の御念仏や年に二度の御八講、折々の尊い営みばかりをなさって、他に何もすることがなく暇でお過ごしですので、この君(薫)が三条宮に出入りなさるのを、かえって親のように、頼もしくお思いになっておられますのが、とてもお気の毒にみえました。冷泉院も帝もいつもお召しになり、春宮も、次々の宮たちも親しい遊び相手としてお誘いになりますので、暇もなく辛いとお思いになって、
「何とかして、身体を分けたいものだ……」などとお悩みでございました。
ご自分の出生について、子供心にかすかにお聞きになった事などを、時折、
「詳しく知りたい……はっきりしないことと思い続けていたけれど、問うべき人もいない。」
母宮に対しては、その事について、事情を知ってしまったと思われるのは心痛むことなので、ずっと心から離れることなくて、
「一体どういうことだろうか。何の因果で、心安からぬ思いが身に添って生まれてきたのか。瞿(く)夷太子が我が身に問うている悟りを得たいものだ……」と、つい独り言が漏れなさるのでございました。
おぼつかな誰に問はましいかにして 初めも果ても知らぬわが身ぞ
(訳)はっきりしないことだ。誰に尋ねたらよいのか。どうして、
初めも終わりも 分からない身の上なのだろう……
答えることのできる人もいない。薫は事にふれ、自分に何か悪い所があるような気がして、尋常でないので、いつも嘆きがあり物思いしながら、
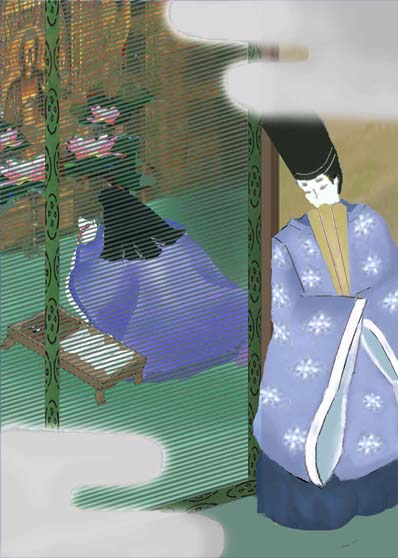 「母宮も、このような盛りの時に尼姿になられ……どのような御道心(本心)から、急に仏道に入られたのだろう。このように、不本意な事が乱れて、きっと全てが嫌だとお思いになることがあったのだろう。世間の人も、これを漏れ聞いて知らないはずがあろうか。やはり隠すべき事があって、私に事情を知らせる人がいないのだろう……」と思われました。 「母宮も、このような盛りの時に尼姿になられ……どのような御道心(本心)から、急に仏道に入られたのだろう。このように、不本意な事が乱れて、きっと全てが嫌だとお思いになることがあったのだろう。世間の人も、これを漏れ聞いて知らないはずがあろうか。やはり隠すべき事があって、私に事情を知らせる人がいないのだろう……」と思われました。
「明け暮れ、母宮は勤行をお勤めなさるようだけれど、計り知れずおっとりとしておいでになる女の悟りの様子は、蓮の露も明らかなように、玉と磨きなさることも難しい。五つの障害(女には五障があり、成仏できないという教え)も、やはり不安であるが、私が母宮の気持ちを助けて、同じ事なら、後世をこそは……」とお考えでございました。
「あの亡くなったと言われる方(柏木)も、辛い思いに迷いが解けずにいるのではないか……」などと察するに、世を変えてでも、対面してみたい気がなさいました。元服(ヽヽ)は面倒にお思いでしたけれど、辞退しきれずに済ませなさいました。自然と世の中から大事にされ、眩いほど華やかなご身辺も気に入らないとのみ思われますので、ただ物静かにおられました。
帝におかれましても、母宮の御血縁へのご厚情が深く、薫君をとても愛しい者とお思いになり、后の宮(明石中宮)も、幼い時から同じ御殿(六条院)にて、明石腹の宮たちと一緒にお育ちになり、遊びなさった頃の待遇を、今も少しも改めようとなさいません。
「一番末にお生まれになり、お気の毒で……、大人になるのを見守ることができない」と、院(源氏)がお思いになり、仰いましたのを思い出しながら、薫を大切な方と思い申し上げておられました。
右の大臣(夕霧)も、ご自分の御子息の君達よりも、この君を心こめて大切にお世話申し上げなさいました。
昔、光君と申した方は、桐壺帝のこの上ないご寵愛をお受けになりましたが、妬みなさる方もあって、母方の御後見がなかったりなどしましたが、源氏の君は、御性格も思慮深く、世の中を穏やかにお考えになっていましたので、並びなきご威光を目立たないように押さえて、遂に、ご自身の人生の最悪の事態になってしまった時にも、無事にやり過ごしなさいました。
来世の勤行の御勤めも時期を遅らせることなく、万事にさりげなく穏やかなご性格の方でございましたが、この君(薫)は、まだ若いうちに、世間の評判が高すぎて、思い上がる事この上なくいらっしゃいます。なるほど、そうあるはずのように、
「とてもこの世の人として、できているのではない……仮に、佛が人間の姿を借りて宿ったか……」と思えることが加わっておりました。ご器量ははっきりと、どこが勝れていて、あぁ、美しいと見える所もないのですけれど、ただとても優美で気品があり、心の奥が深いような様子が、誰にも似ておられません。
薫君の香ばしさこそ、この世の匂いとは思えず、不思議なまでに身じろぎをなさると、その周辺は、遠く離れている所の追い風でも、誠に、百歩の外までも薫るような感じがいたします。どなたも、あれほどのご身分で大層身を窶して、平凡であるようにいられようか。「皆、自分こそ、誰より勝るだろう……」と、さまざまに装い、気遣うはずなのですが、このように体裁悪いほど薫りますと……ちょっとしたお忍びに立ち寄ろうとする物陰に居ても、はっきり薫君と分かるので、隠れようもなく、厄介に思って、香(ヽ)はほとんどお使いになりません。沢山の御唐櫃(からびつ)にしまい込んである香の薫りも、さらに言いようもない匂いが加わるようです。御前の花の木なども、薫君がちょっとお袖を触れになった梅の香りは、春雨の雫にも濡れ、身にしみて感じる人が多くおりました。また秋の野に、主人のいない藤袴さえも、もとの香は隠れて、優しい追い風に、一段と香が引き立つのでございました。
このように大層不思議なまでに、人が気づくほどの薫りに染みておられますのを、匂兵部卿の宮は、他のことよりも競争心をお持ちになって、特別に種々の勝れた香を焚きしめなさり、朝夕の仕事として、薫物を合わせておられました。御前の前栽にも、春は梅の花の園を眺めなさり、秋は世間の人が愛する女郎花や、小さい牝鹿の妻にすめる萩の露にも、少しも御心をお移しにならず、香を忘れる菊や、衰えゆく藤袴、目立たない吾木香などを、凄まじい霜枯れの頃までお忘れにならない様子で、ことさら香を愛する気持を楽しんでおられました。
このようにしていることに対して、
「匂宮は、少し弱々しく優しすぎて、風流な方面にのみ心惹かれすぎている……」と、世間の人は思い申し上げておりました。
昔の院(源氏)は、何事につけても、このように一つを取り立てて、異様なほどに熱中なさる方ではなかったのでございました。
源中将(薫)は、いつもこの宮に参上して、管弦の遊びなどでも、笛の音を吹き立てて競い合い、本気で挑戦するようになさいまして、若い者同士が、好意を持っておられる様子でした。例によって、世間の人は、「匂う兵部卿」「薫る中将」と、聞き辛いほどに言い続けておりました。その頃、年頃の娘がいるような高貴な家々では、婿にと心ときめかして、縁談を申し出たりする人もあるので、匂宮は、様々に興味がわくような家には声をかけて、女性の気配やご様子をお伺いなさいましたけれど、特に御心が留る方はありませんでした。
「ただ、冷泉院の女宮(女一宮)こそ、結婚を考えても良いようだ。その甲斐はあるだろう」とお思いになりましたのは、母女御(弘徽殿)がとても重々しく、奥ゆかしくお過ごしでおいでになりますので、姫君のご様子は、誠に他に類ないほどに素晴らしく、評判も高くいらっしゃいます。まして、身近に伺候し慣れている女房などが、姫宮の詳しいご様子などを、何かの機会に匂宮に申し伝えることなどもありますので、ますます忍びがたく思われるようです。
薫中将は、世の中を味気ないものと、深く悟り澄ましたお気持ちでおいでになり、
「女性に心をよせては、かえって、俗世を離れがたい思いが残るだろう……」などと思うので、煩わしい方面に関係するのは躊躇われる……などと、思い捨てておられました。さしあたり、薫の心に染むような女性の事などがない時には、賢ぶっていたのでありましょうか。親の許しがないような事(結婚)にはまして、思い煩うはずもありません。
十九歳になられた年に、三位(さんみ)の宰相になられ、やはり中将もお辞めになりません。冷泉帝・后の御待遇で、臣下であっては遠慮することもない高貴な人望でおられますが、心の内では、我が身の上について思い当たる所があり、物悲しい気持ちなどがありますので、心のままに、軽率な好色事には全く関心がありません。万事、控えめに振る舞って、自然と年の割に老成したご性格の方として、人からも知られておいでになりました。
三の宮(匂宮)が、年と共に心を砕く冷泉院の姫宮のご様子を見るにつけても、薫君は同じ院内で、姫宮と明け暮れお過ごしなので、何かの折に、姫宮のご様子を聞いたり、拝見したりなさいます。なるほど、姫宮の大層並でなく、奥ゆかしく教養に溢れた御振舞いがこの上なく素晴らしいので、
「同じ事なら、このような女性を妻にすることこそ、生涯楽しく暮らす糸口となるのだろう……」と思われました。帝は、大方のことでは薫君を分け隔てなくお扱いになりましたが、姫宮のご結婚については、薫君をこの上なく遠ざけてなさいますのも無理もない……と、煩わしく思いますので、強いて、姫宮に近づこうとはなさいません。
「もし、思いもよらぬ気持ちが起こったら、自分にも相手にも、とても不都合なことになる……」と、薫は思い知って、近寄ることもありませんでした。
このように女達に愛される人柄なので、ちょっと何気ない言葉をかけた女でさえも、強く突き放す心をなくし靡きやすくなりますので、自然と気の進まない通い所も多くなるのですが、相手に対して、特別なお扱いなどはなさらず、人目をうまく紛らわして、底はかとなく、冷たくない程度の付き合いをなさいました。かえって、女には気がもめることのようで、思いを寄せる女はますます心惹かれて、三条宮に参集する女性は増えるようでした。
薫のつれない態度をみるのも辛いことだけれど、全くお通いが絶えてしまうよりは……と、心細さが辛くて、宮仕えなどしない身分の人々の中で、儚い契りに頼みをかける女性も多くおりました。そうは言っても、魅力のある美しい薫君のご様子なので、一度でも逢う女は皆、騙されるように、大目に見て許してしまうのでございました。
「母宮の生きておられる限りは、朝夕にお側を離れずにお逢いして、お世話を申し上げることを私の生き甲斐としよう……」と思い、そう仰いますので、右の大臣(夕霧)も、大勢いらっしゃる御女(むすめ)たちを、
「ひとりは薫に、ひとりは匂宮に……」と望みながらも、口に出すことがおできになれません。
「何と言っても、近い縁者なので、面白味がない……」とは思ってみるのですが、
「この君達をおいて他には、結婚に相応しい男は、探し出せるだろうか……」と思い悩んでおられました。
高貴な方々よりも、内侍腹の六の君が、とても素晴らしく美しく、ご性格なども申し分なく成長しておられるのに、世間の評判の低いのが、むしろ新鮮な感じがしますので、大臣は不憫にお思いになって、一条の宮(落葉宮)が御子をお持ちでなく、手持ち無沙汰なので、六の君を迎えとって、養女にさせなさいました。
「わざとではなく、この方々(薫・匂宮)に、六の君をお逢わせしたら、きっと夢中になられるだろう。女性の美しさを知る人には、特に格別であろう……」などと、お思いになって、格式張ってお世話なさらず、今風に美しく見えて、趣あるように洒落た暮らし振りをさせて、男の心が夢中になるような工夫をたくさん凝らしなさいました。

賭(のり)弓の還饗(かえりあるじ)の準備を、六条院にて特別に心尽くしなさいまして、親王をもお迎えしようとの心遣いをなさいました。その日、親王たちで大人の方は皆、内裏に伺候されました。后腹の方は、どの方も気高く美しそうにいらっしゃいます。中でも、匂兵部卿の宮は、大層優れてこの上なく見えなさいます。四の御子で、常陸宮と申し上げる更衣腹である方は、思いなしか、気配が格段に劣っていらっしゃいます。
いつものように、賭弓では左方が一方的に勝ちました。いつもより早く終了しましたので、大将は内裏を退出なさいました。匂兵部卿宮、常陸の宮、后腹の五の宮とが、同じ御車に、お招き乗せ申しなさいました。
「親王たちはこちらにおられます。御送りにはおいでになりませんか」と、声をかけ呼び止めて、御子息の衛門の督、権中納言、右大弁など、それ以外の上達部も大勢、あれこれの御車にお乗りになりまして、誘い合って、六条院にいらっしゃいました。
道中、やや時間がかかるうちに、雪が少し散ってきまして、大層風情のある黄昏時です。笛の音を美しく吹き立てながら、六条院に入られますと、
「誠に、ここをおいて他に、どのような佛の国が、このような折節の、心を癒す所として求めることができようか……」と見えました。
神殿の南の廂(ひさし)に、いつものように南向きに、中将や少将がお座りになり、北向きに向かい合って、親王達・上達部(かんだちめ)の御座がありました。御盃などが回り始めて、座が盛り上がってきますと、「求子」を舞いますと、御袖を振返す端風に、御前近くの梅が大層ほころび、溢れる香りがさっと漂ってきますので、いつものように、中将の御薫りがますます素晴らしく引き立って、何とも言えず優美でございました。
わずかに覗いている女房なども、
「闇では、御姿がはっきり見えないけれど、あの薫りは、なるほど他に似たものがありません……」と、薫君を誉め合っておりました。大臣も「誠に素晴らしい……」とご覧になりました。
ご器量や御振る舞いも、いつもより勝って素晴らしく、乱れのない様子でおられますのを見て、
「右の中将(薫)も、ご一緒にお謡いになりませんか。とてもお客人ぶって遠慮しておられますね」と仰いますので、無愛想にならない程度に「神のます」(風俗歌)をお謡いになりました。
源氏物語「匂宮」(第42帖)
平成24年水無月 WAKOGENJI(文・絵)
目次に戻る
|
 ただ、世の常のように、素晴らしく高貴で雅美においでになるので、その様な御一族ゆえ、世間が思い込みとしてお扱い申し上げるご様子が、昔の源氏の君の御威光や有様よりやや勝っていらっしゃるゆえ、このうえなくご威勢があるのでございました。
ただ、世の常のように、素晴らしく高貴で雅美においでになるので、その様な御一族ゆえ、世間が思い込みとしてお扱い申し上げるご様子が、昔の源氏の君の御威光や有様よりやや勝っていらっしゃるゆえ、このうえなくご威勢があるのでございました。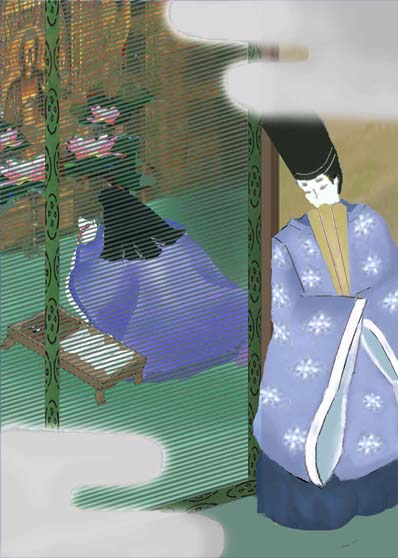 「母宮も、このような盛りの時に尼姿になられ……どのような御道心(本心)から、急に仏道に入られたのだろう。このように、不本意な事が乱れて、きっと全てが嫌だとお思いになることがあったのだろう。世間の人も、これを漏れ聞いて知らないはずがあろうか。やはり隠すべき事があって、私に事情を知らせる人がいないのだろう……」と思われました。
「母宮も、このような盛りの時に尼姿になられ……どのような御道心(本心)から、急に仏道に入られたのだろう。このように、不本意な事が乱れて、きっと全てが嫌だとお思いになることがあったのだろう。世間の人も、これを漏れ聞いて知らないはずがあろうか。やはり隠すべき事があって、私に事情を知らせる人がいないのだろう……」と思われました。