やさしい 現代語訳 源氏物語 「蜻 蛉」 (かげろう) 第52帖 (薰27歳 ・ 浮舟22歳 ・ 匂宮28歳 ・ 中君27歳 ・ 明石中宮46歳 ) 登場人物の 系図 源氏物語の本で読む |
|---|
| 宇治の山荘では、姫君(浮舟)のお姿が見えないので、女房たちが捜して 大騒ぎをしていますけれど、その甲斐もありません。物語に出てくる姫君が 人に連れ去られた朝のようで、詳しく言い続けることもありません。京の母君が、 「先日の使者が、京に帰れなくなってしまったようで、心配しています」と、又、使者を寄越しました。「まだ鶏が鳴く頃に、出立させなさいました」と、使者が言うと、どんなに使者が申し上げようと、乳母をはじめとして、皆、限りなく慌て惑いました。 思い当たる術もなく ただ騒ぎ合うのを、あの事情を知る者達は、ひどく浮舟が物思いしていた様子を思い出して「川に身を投げなさったのか……」と、思い寄るのでした。 泣く泣く母君からの手紙を開けてみますと、とても心配して眠れなかったためか、今宵は、夢の中でさえ、貴女が打ち解けて見えずに、何かに襲われながら、気分もいつものようでなく悪くなり、 ……女二宮の恨みがとても恐ろしく……貴女が京にお渡りになる日が迫ってきましたけれど、その頃に、まず、こちらにお迎え申しましょう。今日は雨が降りそうですので……」などとありました。 昨夜の母君への返事を開いて見て、右近はひどく泣きました。 「やはりそうか……姫君は心細いことを申しなさっていました。この私に何故少しでも仰らなかったのか。幼い頃から、心置きなく、少しも心隔てなく暮らし馴れていましたのに、死出の別れ道にさえ、私に気配さえも見せなさらないのが情けないこと……」と思いますと、足ずりして泣く様子は幼い子供のようでした。「ひどくお悩みのご様子は 私もずっと拝見してきましたが、このように普通では大それたこと(入水)を思いつくようには見えなかった姫君のお気持ちを、やはりどうなさったのか…と分からずにいたことが、大層悲しく思われました。 乳母は、かえって何も分からずに、ただ「どうしよう、どうしよう」と口走っていました。 匂宮も、誠に、いつもと違ったご様子であった御返事に、 「どのように浮舟は思っているのだろう。私をやはり愛している様子ながら 浮気な心(ヽヽヽヽ)とだけ深く疑っていたので、どこか他所へ行き、身を隠してしまったのか……」とお思いになりました。 大騒ぎしているところに 宮からの使者が参りました。山荘にいる者 皆が泣き惑う中、使者は御文もお手渡しできずに、「一体どうしたのか……」と、下衆女に尋ねますと、 「上様(浮舟)が今宵、急にお亡くなりになったので、人々は何も分からなく混乱しておいでです。頼もしい人(薰)もおられない折なので、お仕えする人々はただ 物に突き当たったように 心惑っておられます」と申しました。 使者は 事情も深く知らない男で、詳しく質問もしないまま京に帰り、「このようでございました」と報告申し上げましたところ、匂宮は「まさか悪夢か……」とお思いになって、 「とても変だなぁ……浮舟が重く患っていたとも聞いていない。日頃、気分が悪いとばかり書いてあったけれど、昨日の御返事には変わったこともなく、いつもより情緒があったものを……」と、思い当たることもありません。 「時方、宇治に行って様子を見て、確かなことを尋ねてきなさい」と仰いました。時方は、 「あの大将殿(薰)は、どのようなことか お聞きのこともございましょう。誠に、宿直をする者が劣かであった……と、戒め仰ったとして、下人が退出するのさえ、宿直が見咎め質問するそうですので、言い繕うこともなく、時方が宇治に来たと漏れ聞いたら、薰大将がお気づきになることがありましょう。さらに、急に人がお亡くなりになった所は当然騒がしく、人々が多くおりますので……」と申し上げました。宮は、 「そうといっても、大層気掛かりなままでいられようか。やはり然るべき様子に取り計らって、いつもの 事情を知る侍従などに会って、どういう訳で 使者がこのように言うのか 尋ねなさい。下衆は、間違ったことを言うものだ」と仰いますので、時方は、宮のお気の毒なご様子も畏れ多く思われて、夕方、宇治へ出立致しました。 身軽な者(時方)はすぐに宇治に着きました。また雨が少し降り 止んだけれど、木幡山の理屈に合わないほど険しい道を、目立たぬよう下衆の姿に変えて来ましたところ、山荘内は人が大勢立ち騒いでいて、「今夜、このまま亡骸をお納め(埋葬)申し上げることにしよう……」等と、人々が言うのを聞き、呆れるほど情けなく思われました。右近に連絡を入れましたけれど、会うことができませんでした。右近は、 「今は 何も分からず……起き上がる気持ちもしません。それにしても、今夜を最後に……このようにお立ち寄りなさっても、何も申し上げることはありません」と、取次ぎの者に言わせました。 「そうは言っても、このように事情がはっきりしないまま、私はどうして京に帰ることができましょう。せめてもうお一方(ひとかた)にでも……」としきりに言いましたので、侍従が会いました。 「とても呆れたことで、姫君(浮舟)が、思いがけない様子でお亡くなりになりました……大変悲しい……と、言っても言い尽くせず、悪夢のようで、誰もが困り果てております……と、匂宮に申し上げてください。私が少し気持ちが落ち着きましたなら、日頃 物思いしていた姫君のご様子や、昨晩、本当に心苦しい…と、宮のことを想い申し上げなさっていた事などもお聞かせ申しましょう。この穢(けが)らい(けがれ)など、人が忌む期間が過ぎてから、もう一度お立ち寄り下さい」と言って、大層酷く泣きました。邸内にも泣き声ばかりして……乳母なのでありましょう。 「わが姫君は どこに行ってしまわれたのか……お戻りなさいませ、空しい亡骸を拝見しないのが、甲斐もなく 悲しいことでございます。明け暮れ、私が拝見していても、わが姫君は一日中、物思いなさっていて、いつしかご立派なご様子を拝見申し上げたい……と、朝夕、お頼み申し上げていたので、私の命も延びましたのに、私をお見捨てなさって、このように行方も知らせなさらぬとは……鬼神様も、わが姫君を手に入ることができまい 皆が大層惜しむ人を、帝釈天もお返しになると申します。姫君をお取り申したのは、人であれ、鬼であれ、お返し申してください。亡骸を私は拝見したいのです……」と言い続けるが、承知していない事柄が混ざるのを不思議と思って、時方は、 「やはり総て仰ってください。もしや誰かが姫をお隠しになったのか。私は、確かなことを聞いてくるようにと、匂宮がご自身の代わりに、出立させなさった使者でございます。今はとにかく、何の甲斐もないことですが、後でお聞き合わせなさることもあるでしょうから、私の報告と違うことが混じれば、参りました使者の罪となるでしょう。また、そのようなことはあるまいと宮が信頼なさって「貴女たちに会いなさい」と仰ったお気持ちを、畏けないとお思いになりませんか。女の道に迷いなさることは、外の朝廷にも古い例などがありましたが、又、このようなことはこの世にはないとだけ拝見しております」と言うので、 「誠に……大層お気の毒な使者ですこと。私が隠そうとしても、こうして、例のないことの詳細は、自然に匂宮のお耳に入ることでしょう」と思って、侍従は、 「どうして、ほんの少しでも『誰かが姫君をお隠しなさったのだろう……』と思い当たることがあったなら、このように皆で大騒ぎすることがありましょうか。日頃、大層酷く物思いしているようなので、あの殿(薰)が煩わしげに、匂宮との仲をほのめかし、姫君に仰ることなどもありました。御母君も、大騒ぎする乳母なども、「初めから知り始めていた方(薰)の所にお渡りになるだろう……」と準備して、匂宮との仲を人に知られないように隠して、殿には「畏れ多くもったいない」と思い申し上げておいでになりましたので、お心も乱れたのでしょう。驚くべき事ですが……姫君がご自分から、心と身を亡くしなさったようなのです…と、さすがにありのままではなく、事実をほのめかし話しました。時方は承知しがたく思われて、 「それならば落ち着いてから参りましょう。立ち話で済ませるのも、とても簡略なよう……いずれ、匂宮ご自身でも、おいでになることでしょう」と言いますと、侍従は 「あぁ、畏れ多いこと。今更 周囲がお二人の仲を知り申すことも、亡き姫君の御ためには、かえって素晴らしい御宿世と見えることですが、姫君がお隠しになっていたことなので、匂宮もまたお漏らしなさらずに終わりになさることが、亡き姫君の御心に従うことになりましょう。ここ宇治ではこのように、世に稀な様子でお亡くなりになったことを、世間に聞かせまいと、万事に紛らわしているけれど、自然と事件の様子も見えてしまう……と思われるので、時方を急かして帰らせました。 激しく降った雨に紛れて、母君も 宇治においでになりました。更に言いようもなく、 「目の前で亡くなられた悲しみがどんなに強くとも……死は世の常 よくあることですが……これは、一体どうしたことか……」と、大層心乱れておられました。 匂宮とのことを隠していましたので、姫君が大層物思いなさっていた等とは知らずに、身を投げた…などとは思いもよらず、 「鬼が喰ったか、狐のような魔物が連れ去ったのか、昔物語にある怪しい事件の例か……そのような事も言っていたが……」と母君は思い出していました。 「それとも 浮舟が恐ろしいと思っていた女二宮(薰の正室)の辺りで、悪い心を持つ乳母が、近々 大将殿が 浮舟を京にお迎えになると聞いて、目障りに思って、姫を騙し隠したのだろう……」と、母は下衆たちを疑い、新参者で気心の知れない者はおりませんか…と尋ねました。女房は 「都から遠く離れている」と言って、宇治に住み馴れぬ女房は、ここでは何事も不自由なので……、またすぐに参ります」と言っては、皆、引越しの荷物を持って、京に帰ってしまいました」と答えました。以前から居る女房でさえ、半分は居なくなって、今の山荘は人が少ない時でございました。  侍従などは、浮舟の日頃のご様子を思い出して「死んでしまいたい……」と、泣いていらした折に「亡き影に添えてほしい……」と書き置きなさいました手紙が、硯の上下にあるのを見つけて、川の方を見やって、恐ろしげに響き渡る水の音を聞くと、「大層気味悪く 悲しいこと……」と思い、 「亡くなられた姫君のことを あれこれ言い騒いで、誰もが『どのようにお亡くなりになったのか』とお疑いなさるのも、お気の毒なことだ」等と、相談し合って、 「匂宮との秘め事も、姫御自分から引き起こしたことではないのですし、母君としても、姫君亡き後に お聞きになったとしても、相手が とても高貴な匂宮ならば、誇りにも思えましょう。 ありのままにお話し申し上げて、このように物事が曖昧な事があっても、あれこれ思い悩んでいらっしゃる様子を、少しはっきりさせて上げましょう。亡くなられた方としても、亡骸を安置して葬儀を行うのこそ、世間一般ではありますが、世間と違う様子で幾日も過ぎれば、更に事実を隠しおおせないでしょう。やはり母君に申し上げて、今は世間の噂だけでも繕うことに致しましょう」等と話し合って、浮舟の在りし日の様子をお話し申し上げると、言う人も正気を無くして言い続けることができません。 母君も聞く気持ちが大層乱れて、 「それでは、この大層荒々しい川に流されて、亡くなってしまわれたのか……」と、ますます自分も川に落ち入るような気持ちがして、 「流れて行かれた方向を捜して、せめて亡骸だけでも きちんと葬りたい……」と仰いましたが、 「更に、何の甲斐もありません。行方も知れない大海原に行かれたのでしょう。それなのに、人が言い伝えることは、とても聞き辛い……」と申しますので、母君はあれこれ思うと 胸がこみあげる心地がして、どうにも なす術もなく思われました。 この女房二人して、浮舟方に車を寄せさせて、御座(おまし)など身近でお使いになっていた調度品や、脱ぎ置きなさった御襖(ふすま)等のようなもの等を車に積み込みました。乳母子の大徳やその叔父の阿闍梨、その弟子の親しい者等、昔から知っていた老法師などの 御忌中に籠もるべき者だけで、人が亡くなった時の規則に真似て 車を出立させましたので、乳母や母君は「大層不吉……」と倒れ転んでしまいました。大夫や田舎人など、浮舟をおどし申した者たちもやってきて、 「御葬送のことは殿(薰)に事情を申し上げて、日程を決めて、厳かにお仕え申し上げるように…」と言いましたけれど、 「特別に、今夜すぐに執り行いたいのです。大層忍んで(ヽヽヽ)と思うところがありますので……」と言って、この車を向かいの山の前にある野原に行かせて、人々を近くに寄せず、この事情を知る法師たちだけで焼かせました。煙は、大層はかなく消えました。宇治の田舎人たちは、かえってこのような弔いを仰々しくして、こと忌みなど心深くする習慣なので、 「誠に怪しい。決まりの作法など、あるべきことをなさらずに、いかにも下衆のように、あっけなく済ませなさったものだ……」と非難しますと、 「兄弟のいる人は、わざと簡素に弔いなさいます。京の人は……」などと、いろいろと良くないことを言っていました。 このような田舎人が とやかく言うことでさえ 慎むべきことであるのに、まして、噂が広がる世間では、大将殿(薰)の辺りで「亡骸もなく、浮舟は亡くなられた……」とお聞きになったら、必ずや、お疑いになる事があるでしょうけれど、匂宮もまた、同じ親しい仲間でおられるので、浮舟が居る居ないは 少しの間は隠すと思われますが、遂には明らかになるでしょう。 薰大将もまた、宮こそを お疑い申し上げることはなさらないで、 「一体、どのような人が浮舟を隠したのだろうか……」などと、お思いになることでありましょう。 生きておられた頃の御宿世は、大層 気高くおられた姫君が、誠に……亡くなられた後には、酷い疑いをかけられることか……」と思えば、この山荘にいる下人達で、今朝の慌ただしかった大騒ぎを見聞きした者には、口止めをして、事情を知らない者には何も聞かせまい……」などと、右近は誤魔化しました。女房は、 「長い月日が経ったら、どなたにも静かに、浮舟の在りし日のご様子を申し上げましょう。ただ今は、悲しみが覚めるようなことを、ふと人伝にお聞きなさるのは、やはりとてもお気の毒なことになるでしょう……」と、この二人は心に鬼が住んでいるのか、必死に真実を隠すのでした。 大将殿は、入道の宮がご病気になられたので、石山にお籠もりなさいまして、御修業にお忙しい頃でした。ますます宇治のことが気掛かりに思われましたけれど、はっきりと説明する人がいないので、このような大それた事件にも、まず御使者が来ないのを「世間の目も辛い……」と思いましたが、御荘園の者が参上して「これこれしかじかです」と申し上げましたので、驚き呆れた心地がなさって、その次の日の早朝に、御使者を弔問に参上させました。 「大変悲しいことです……すぐに自ら出向くべきところ、母宮(女三宮)がご病気ということで、身を慎んでこの石山に、日数を限って籠もっております。昨夜の葬送のことは、どうして……私に連絡をして、日を延期してでも 執り行うべきことなのに、大変簡素な形で 急いで催しなさったのか……。とにかく今となっては、言う甲斐もないことですけれど、最期の行事でさえ、山里の人々の非難を受けるとは、私には大層辛いことでございます……」などと、殿に親しい大蔵の大輔(仲信)を通して仰いました。 御使者が来たのにつけても、ますます悲しく 申し上げようもないことなので、宇治の人々は涙に溺れるばかりの様子なのを口実として、きちんと御返事も申し上げられませんでした。 殿は「やはり大変あっけなく……悲しいことだ」とお聞きになり、 「何ともここは辛い所(宇治=憂し)だなぁ、鬼などが住んでいるのか……どうして今まで そんな所に浮舟を置いておけたのか……思いがけない方(匂)との過ちがあったようなのも、私が浮舟を放って置いたので、匂宮も 気楽に言い寄りなさったのだろう……」と、自分の緩んだ 世間慣れしていない心を口惜しく、胸が痛くなる思いがなさいました。 母宮の御具合の悪い時に、このようなことで思い乱れるのも不都合なので、一旦、京にお帰りになりましたが、女二宮(正室)の御邸にもお渡りにならず、 「大した事ではないのですが、不吉なことが身近にありましたので、心の乱れる間は慎んでおりまして、不吉なことですので……」と申し上げなさって、尽きせず無常の世をお嘆きになりました。浮舟の在りし日の容姿や、大層魅力的で美しかった雰囲気などが、大層恋しく悲しいので、 「現世では、私は どうして浮舟に夢中にならずに、のどかに過ごしてしまったのだろうか。浮舟亡き今、この悲しみを鎮める方法もないままに、悔しいことが数知れない。私はこのような男女のことにつけて、酷く物思いをする運命なのだろうか。世間の人と異なって、仏道を志した人生のはずなのに、思いのほかに、普通の人のように、命永らえることを、仏が憎いとご覧になるのだろうか……人に仏心を起こさせようとして、仏のなさる教えは 慈悲をも隠して、こうなさるのか……」と思い続けながら、勤行などを一心になさいました。 あの匂宮は、また二、三日は何も考えられず、正気のない様子で、 「どのような物の怪だろうか……」などと騒ぐうちに、涙を流し尽くしなさいました。だんだんお気持ちも鎮まってきますと、姫の生前のご様子を恋しく悲しく思い出されました。 周囲には、ただ病気が重い様子だけを見せて、 「このようなむやみに悲しそうな目つきを、他人には知らせまい……」と、賢く隠そうとなさいましたけれど、自然にはっきりと分かるので、 「どのようなことに、宮はこれほど思い悩み、御命の危ないほどに 沈み嘆いておられるのか……」と言う人もありました。 あの殿(薰)は とても詳しく 宮のご様子をお聞きになって、 「そうであったか……やはり、浮舟とはただの文通をするだけの御仲ではなかったのだ。匂宮もお会いになって、必ず夢中になってしまうはずの女であった。もし長生きしていたなら、ただの御仲より、自分のためには良くないことも 出てきたことだろう……」と、浮舟への恋い焦がれる気持ちも、少し冷める心地がなさいました。 匂宮のお見舞いに、日々参上なさらない人はないほど、世間の大騒ぎとなっている時、薰大将は、 「大した身分でもない女のために 閉じ籠もって、お見舞いに伺わないのも 不都合な事だろう……」とお思いになって、匂邸においでになりました。その頃、式部卿宮と申し上げる宮も亡くなられましたので、御叔父の服喪の服で、薄鈍色の着物をお召しになって、浮舟の服喪にも思いを寄せられ、心中はしみじみと悲しげに 相応しいご様子でございました。少し痩せて、ますます優美なご様子が勝っておられました。 お見舞いの人々は匂宮邸を退去して、ひっそりとした夕暮れ時でした。宮は臥して 沈み込んでおられまして、疎遠な人にはお会いになりませんが、いつも御簾の内にお通しして対面なさる方には、お逢いにならないこともできません。宮は何となく気が引けましたが 対面なさいますと、ますます涙が止めがたく……ようやく心を鎮めなさって、 「それほど深刻な病状ではありませんが、皆が「大事になさるべき病……」と申しますので、父帝や母宮もご心配下さるのが、とても心苦しく思われます。誠に、世の中の無常を大層心細く思っております……」と仰って、押し拭い 紛らしなさる涙が、やがて留まらずに流れ落ちたので、大層体裁悪いことだけれど「 必ずしも浮舟の死故の涙と、どうして気付くだろうか。ただ女々しく心弱い者と見ることだろう……」とお考えでした。大将は、 「そうだったのか……ただ浮舟の亡くなったことだけを、宮は悲しんでおられたのか……お二人の関係は いつからなのだろう……私をどんなに滑稽だ…と物笑いなさる気持ちで、幾月も過ごしておられたのだろうか…」と思うと、悲しみが消えたようにさえ思われました。 一方、匂宮は、 「何と薄情な方なのであろうか。物事を切に思う時は、このような事につけてさえ、空飛ぶ鳥が鳴き渡る様子にさえ気持ちをそそられて悲しいものだ。私がこのように何となく心弱くなっているにつけても、もし大将が真実を知っていても……それ程 物のあわれを知らない人でもあるまい……。世の中の無常を 心に染みて思える人でさえ、どうしてこのように冷淡でいられるのか……」と羨ましくも、心憎くも思われる一方で、女との縁を思うと しみじみ感慨深く、浮舟がこの君と向かい合っている様子を想像して、「形見ではないか……」と見つめておられました。  匂宮が、だんだんと世間話を申し上げなさると、薰大将は、 「浮舟のことを、これ以上隠しておくこともできないだろう……」とお思いになって、 「昔から、貴方に申し上げなかったことを心に秘めて残している間は、酷く気分が晴れないと存じていましたが、今は、私もだんだん身分も高くなりました。それ以上に、貴方様が御暇もないご様子で、心のどかにおられる時もありませんので、宿直など特に用事がなくては、伺候することもなく過ごしてしまいました。 実は、昔、ご覧になった宇治の山里にて、儚く亡くなった大君と同じ縁続きの人(浮舟)が 思いがけない所に居ると聞きつけまして「時々 逢おうか……」と思っておりましたが、不都合にも、世間の非難もあるような時でしたので、心ならず 山里に放置しておりました。 京から出かけて行って逢うこともないまま……また、その浮舟も、私独りを特に頼りにする心もなかったようで……高貴な重々しい扱いをすべき人とは思われず、世話をするには、特に咎められることなどもありませんでした。 気楽で可愛らしい人と思っておりましたが、大層あっけなく 自死してしまいました。すべて世の無常を思いますと、悲しいことでございます。浮舟のことはお聞き及びのことでございましょう……」と、今こそお泣きになりました。 この君(薰)は、 「大層な悲しみはお見せするまい。愚かなことだ……」とお思いでしたが、涙が溢れだして、とても止め難い様子で、少し取り乱した表情でおられますので、匂宮は 何ともお気の毒な事とお思いになり、あえて すげない様子で、 「大変お気の毒なことでございます。昨日、私も少し聞きました。どのようにお見舞い申し上げようかと思いながら、特別に世間にはお知らせなさらないと聞いておりました」等と、つれなく仰いましたが、とても堪えがたいので、言葉少なくおられました。 大将は、 「そのような人として、宮にもいづれご覧頂こうと思っていた女でございます。自然とそのようなことにお気づきでしたでしょうか。宮邸にも出入りする縁故もありましたので……」などと、少しずつ、事情を仄めかして、 「ご気分が良くないうちは、つまらない世間のことをお聞きになって 驚きなさるのも、不都合なことでございます。どうぞお大事になさいますように……」などと申し置いて 退出なさいました。 「浮舟のことを強くお想いであったようだ。大層あっけなく 亡くなったけれど、やはり高い運勢の方であったようだ。匂宮は 今上帝や后宮が大切にお育てなさった親王で、ご容貌をはじめとして、今の世には、他におられない方だ。寵愛なさる夫人も 並一通りではなく、様々につけて この上ない方をさし置いて、この浮舟に御心を尽くし、世間の人が大騒ぎして、修法・読経・祭り・御祓いと、それぞれの道で騒ぐのは、この浮舟を愛するが故の 匂宮の御気持ちの誤りであったのだろう。 私も、こればかりの身分で、今上帝の御娘(女二宮)を頂きながら、この浮舟が愛しく思えたのは……宮に劣っていようか。それ以上に「今は亡き人……」と思うと、心を鎮める方法さえもない。 そうは言っても愚かなことだ……そうなるまい」と思い堪えましたが、様々に心乱れて、 「人は木や石ではなく、皆、感情を持っている……」と口ずさみなさって、臥せっておられました。 浮舟亡き後の葬送などについても、大層簡略に済ませたことを、 「中君は どのようにお聞きになるのか……」とお気の毒に思い、お慰めの仕様もありませんでした。 更に、大将は、 「浮舟の母君が普通の身分なので『兄弟のある人は、後に残った弟妹のために葬儀を簡略にする…』という世俗の言い伝えがあるのを鑑みて、簡略に済ませたのだろうか……」 誠に気に入らない事だとお思いになりました。宇治のことが気掛かりなのも限りないので、浮舟のその折のご様子を、ご自身で聞きたいとお思いになりましたが、 「宇治に長く籠もるのも、不都合であろう。行っても直ぐ立ち返るのも心苦しいことだ……」等と、思い煩っておられました。 月日が経って「今日こそ、浮舟を京へ迎える日だった……」と、思い出しなさいました日の夕暮、薰大将は、誠にもの悲しくなられました。御前近くの 橘の香りが優しく感じられる時に、時鳥(ほととぎす)が二声鳴いて渡りました。「亡き人の宿に通うならば……」と独り言を仰って、何かもの足りなく淋しくお感じになりました。ちょうど北の宮(二条院)に、匂宮がお渡りになる日だったので、橘の枝を手折らせて、御文をお書きになりました。 忍びねや君も泣くらむ かひもなき 死出の田長(たおさ)に心通はば (訳)時鳥が忍び音で鳴いて渡ります。貴方も泣いておられましょうか 泣いても甲斐のない死に旅立った方に、心を通わせて…… 匂宮は、中君の御姿がとても浮舟に似ているのを 悲しくお思いになって、しみじみと物思いをしているところでした。「意味ありげな御文だなぁ……」とご覧になって、 たちばなの薰あたりは時鳥 心してこそ泣くべかりけれ わづらはし…… (訳)橘の薰る辺りは 時鳥よ、気をつけて鳴くものですよ。迷惑なこと…… と、お書きになりました。 中君はこの事情については全てお分かりでした。 「しみじみと意外なほどあっけなかったそれぞれ(大君と浮舟)につけても、心深いなかに、自分一人が、物思いを知らないまま 今まで命永らえていたのか……それもいつまで続くことか……」と心細くお思いになりました。匂宮は、隠し事をなさるのも とても苦しいので、浮舟との在りし日のご様子などを、少し取り繕いながらお話しになりました。 「貴女が隠し事をしていらっしゃったのが、私には辛かった……」などと、泣いたり笑ったりしながら申しなさいますので、他の人よりは親しみを感じて、悲しくおいでになりました。 匂宮のご病気で、大袈裟に ご立派に 大騒ぎをなさる六君方では、父大臣・兄の公達など、御見舞い客が頻繁で煩わしいのですが、ここ(中君方)は、大層気楽で慕わしいとお思いでした。本当に、夢のようにお思いになって、やはり「どうして、とても急なことであったのか……」と、気分が晴れないので、いつもの時方をお呼びになり、右近を迎えに使わしなさいました。 母君もそれ以上に、この川の音や気配を聞くと 自分も川に引き摺り込まれてしまいそうで、悲しく辛いことが休まる暇もないので、ひどく寂しく 堪えがたく思われ、京にお帰りになりました。 宇治では、念仏の僧たちを頼りに読経を済ませて、大層ひっそりとしている時に、匂宮の御使者がやって来ました。当時、厳重に警戒していた宿直人たちも、今は見咎めいたしません。 「あいにく最期の時に、匂宮をお入れすることが出来ないままになってしまった……」と思い出すのも、お気の毒なことでございました。供人は、 「とんでもない女に、匂宮は執着なさったことよ……」と、当時は見苦しく拝見していましたが、 ここ宇治に来てからは、宮がおられる夜の有様や、宮に抱かれて 小舟にお乗りになった感じが上品で可愛らしかった……」と思い出すと、心強くいられずに、しみじみ感慨深くおりました。 右近がお会いして 大層泣きますのも、当然なことでございました。時方が、 「匂宮が仰いますので、このように御使者として参りました」と申しますと、右近は、 「今更、人が『姫君の死は変(ヽ)だ……』と言ったり、思ったりするのも気が引けて……。匂宮方に参上しても、はっきり 納得なさる程に、ご説明申し上げられる気がいたしません。この忌中が終わって、 「ありのままには こうでした」と言っても、納得頂けるかどうか……少し相応しい頃になってから、もし思いの外に 私がまだ生きておりましたなら、少し気持ちが静まった頃に、宮の仰せがなくとも御前に参上して、まるで夢のようだったことを、お話し申し上げたいと存じます…」と言って、今日は全く、動く様子もありません。大夫(仲信)も大層泣いて、 「その上、私は、このお二人の仲のことを、細かくは存知ませんし、物の道理を弁えていません。 匂宮のこの上ないご寵愛を拝見しましたので、貴女たち女房を、今後はどう受け入れ申しましょう。いずれは親しくお仕え申すべきあたりの方々と思っておりましたが、言う甲斐なく悲しい事の後には、私の悲しみもかえって深く勝りまして……」と申しました。さらに、 「わざわざ匂宮が 御車でお迎えを差し向けなさっったのに、空しく帰るのは残念でなりません。今どなたか一方(ひとかた)でも、匂宮邸に参上なさって下さい……」と言いますので、右近は侍従の君を呼び出して、「では 貴女が参上なさいませ」と申しました。侍従は、 「それ以上、何事を申し上げることがありましょう。やはりこの忌中の間には……。どうして匂宮はお弔いさせて下さらないのでしょう」等と答えました。 「宮がご病気の影響で、様々な御慎み事があるようで、忌明けを待ちきれないご様子です。またお二人の深い御契りでは、宮は暫くお籠もりなさるのでしょう。忌明けまで残りの日、幾日でもありません。やはりお一方、おいでになって下さい」と責めるので、侍従は、 「今は、匂宮のご様子が大層恋しく思われます……いつの世にか、再び匂宮にお逢いできましょうか。このような折にこそ……」と思い、参上することに致しました。 黒い衣(きぬ)の装束を着て、身なりを整えた姿も とても美しく見えました。裳は、自分より身分の上の人はいないと気が緩んで 鈍色に変えずにいたので、紫の薄い色の物を持たせて、参上致しました。 「もし生きておられたら、この道を忍んでお出でになったことでしょう。私も人知れず、宮に心寄せ申し上げていたので……」等と思うと とても悲しいので、道すがら、泣きながら参上致しました。 匂宮は、「侍従が参りました……」とお聞きになるにつけても、悲しんでおられた女宮には、あまりに憚られるので、何も申しなさいません。宮は寝殿におられましたので、寝殿にて侍従を降ろしなさいました。 在りし日の浮舟のご様子などを 詳しくお尋ねなさいますと、 「日頃、お嘆きになっていた様子や、その夜 お泣きになったご様子は……不思議なほど言葉少なで、 ただぼんやりしておられまして、『大変だ…』とお思いのことさえも、人に打ち明けることはなさらず、包み隠しなさったせいか、言い残す言葉(遺言)などもございません。夢にも、このように、入水(ヽヽ)などをお覚悟なさったとは、私共 思いもしませんでした……」等と 詳しくお話し申し上げますと、匂宮は大層酷く悲しまれ、 「そのように亡くなったとは……ともかく病死よりも、どんなにか強いお覚悟のもとに、流れる川に溺れてしまわれたのか……それを見つけて、堰き止めたかった……」と、心が煮えたぎる思いがなさいましたが、今となっては どうしようもありません。 匂宮が、 「御手紙を焼き失いなさったことなどを、なぜ不審に思われなかったのですか……」等と、一晩中、お聞きになりますので、お話し申し上げながら、夜を明かしました。あの巻数に書き付けなさった母君の返事(かえりごと)などについても申し上げました。何ほどの者とも思わなかった この侍従に対しても、とても慕わしく お気の毒にお思いになって、 「私のもとに居なさい。あの中君とも 縁のない人ではないのだから……」と仰いますので、 「宮に伺候することは、何とも悲しく思われますので、今、忌中を過ごしてから……」とお答え申し上げました。 匂宮は、「又、きっと参りなさい……」と、この侍従とさえ、別れがたくお思いになりました。 早朝、侍従が帰る時に、浮舟の御料として整えなさった 櫛の箱一具・御衣箱の一具を、贈り物にお与えなさいました。浮舟のために様々に整えさせた物は沢山ありましたけれど、仰々しくなるので、ただ侍従に相応しい程になさいました。 「何も考えずに 二条院に参りまして、このような物を頂いたことを、女房達はどのように見るのだろうか。何となく煩わしい……」と思いましたが、どうして辞退など申し上げられましょうか……右近と二人で、所在ないままに、今風に細かく仕上げた御道具が集めてあるのを見ながら、ただただ悲しみにくれておりました。御装束なども、とても優美に仕立てた物ばかりで、 「このような服喪の間、これらをどう隠したらよいものか……」などと困っておりました。 薰大将殿もやはり「誠に不審な事だ……」と思い余って、遂に 宇治においでになりました。 道中、昔のことなどを思い集めて、 「どのような御縁で、この親王(八宮)のもとに 私は通い始めたのだろう。このように思いもかけなかった姫君の最期までお世話をして、八宮の縁(家族)につけては、物思いばかりすることだった。八宮が大層尊くおられたところで、仏のお導きによって「来世を……」とばかり祈願していたけれど、心汚い末の思惑違いによって、仏が世の無常をお教え下さったようだ……」とお思いになりました。 右近をお呼びになって、 「生前の浮舟のご様子もはっきりと聞かずに、 呆れるほどあっけなく亡くなられ……忌中の残りの期間も少なくなりました。それが過ぎてからと思ったけれど、心を鎮め抑えることができずにやって来ました。浮舟はどのようなご様子で、急に亡くなられたのですか……」とお尋ねになりました。 右近は、 「辨の尼君も 浮舟のご様子はよく知っているので、いつかは尼君にも、聞き合わせなさるだろうから、なまじ隠し事をして、事実が違って聞かれるのも、不都合なことになりましょう。匂宮とのあるべきでない話については、今まで嘘をも交えて 思い巡らせて 言い繕ってきたけれど、薰大将のように真面目な方と 向き合ってお話し申し上げると、『ああ言おう……こう言おう……』と、前もって用意していた言葉を忘れ、煩わしいことだ……」と思えたので、浮舟の在りし日の事を、ありのままにお話し申し上げました。 薰大将は、唯々驚き呆れ、思いがけない事なので、暫くは一言も仰いませんでした。 「何とも、あるべきことではない……」と、普通の人が思ったりするようなことを、この上なく言葉少なに仰って、 「おっとりした姫(浮舟)が、どうして入水(丶丶)という恐ろしい事を思い立ったのだろう。この二人は、どのように言い繕って言うのだろうか……」と、御心もさらに乱れなさいましたが、匂宮がひどく嘆いていたご様子をはっきり見たし、山荘の人々も、素知らぬ振りを装ってる態度が、自然と見えたので、大将殿がこのように宇治にお出でになって、 「悲しく酷いこと……身分の上下の人達が集まって、皆、泣き騒いでいる……」とお聞きになると、 「お供をしていて、居なくなった人はないか。やはりその時の様子を、確実に全て 話しなさい。 浮舟が私を疎かに思って 背きなさることは、決してないと思うので、何か 急に言い知らぬ事があって、入水(丶丶)の如きことをなさったのか……私には信じることができない」と仰いました。 右近は、 「大層お気の毒なことですけれど、やはり心配したとおり……」と、煩わしく思って、 「自然とお聞きでございましょう。浮舟はもとから、不遇なお育ちをなさいまして、常陸に下りなさった後、人里離れたお住まいで暮らした頃には、いつとなく物思いばかりしていたようです……。 たまたま 薰大将殿が宇治にお渡りになるようになり、それをお待ちになることで、昔からの身の上の嘆きを慰めておいでになりました。時折お逢いになるようになり……言葉に出しては仰いませんでしたが、ずっと想い続けていらっしゃいました。 京に迎えられるという御本意が叶うと承ったことがありまして、こうしてお仕えする女房たちも、嬉しいことと準備を急ぎました、あの筑波山の母君も やっとのことで念願叶った様子で、京に渡る御準備をなさっていたのに、ある日、大将殿より納得のいかない御手紙がありまして、 『ここに宿直等で仕える者どもや、女房達がだらしないようだなどと、厳しく仰せになった……』として、物の道理を弁えない荒々しい田舎人などのせいであるかのように、取りなすことなどございましたが、その後、久しく御手紙などもありませんでしたので、 「情けない身の上……」と、幼い頃から思い知っていたものを、 何とか一人前に扱われるようにと 育ててきた母君が、その事により 人から物笑いされたら、どんなにお嘆きになるだろう……と、いつも嘆いていらっしゃいました。 『そのことより外に、何が原因なのか……』思い当たることはありません。鬼などが姫を隠し申したら、いささかの残る物があるでしょうに……」と大層泣きますので、 薰大将は、 「どのようなことか……」とお疑いの気持ちも失せ、涙に咳き込んで抑えられません。 「私は自分の思い通り振る舞うこともできず、今上帝から 際立ってもてなされる身分でもあるために、気がかりとは思っていても、『いずれ身近くに迎えて、不安なく気楽にもてなして、行く末長く……』との思いを抑えながら過ごしていましたのに、浮舟が 私を冷淡だとみなされたのは、きっと、他に心寄せる人でもあったのだろうか……。 今更 こうは言うまい…とは思うが、他に人が聞いているならともかく……匂宮とのことは、いつから始まったのですか。それが原因で……大層不都合に 女の心を惑わしなさる宮なので、いつも私と逢えないという寂しさに、ご自身の御心を失いなさったのか……もっと詳しく言いなさい。私には これ以上 隠し事をなさるな……」と仰いました。 右近は、 「既に 確かなことをお聞きなのだゎ……」と、とても困って、 「大変嫌なことをお聞きになったようです……私も、浮舟の側に伺候していない折はありませんでしたものを……」と物思いに耽って、躊躇いながら、 「自然と お耳に入った事でしょうけれど、この宮の上(中君)の所に、浮舟が忍んでお渡りになった時、何とも呆れて思いがけないことに、匂宮が、浮舟の居間にお入りになりました。私共が大層厳しいことを申し上げて、退出していただきましたが、姫君はそれ以降とても恐がりなさって、中君のもとを離れて、あの見窄らしい三条の隠れ家にお移りになりました。その後 世間の噂にも知られてはならない……として、逢瀬は終わりになりましたのに……。 匂宮はどのようにお探しになったのでしょう。ちょうどこの二月頃から、宇治に訪れなさいました。御文は幾度もありましたが、浮舟はご覧になることもありませんでした。大層畏れ多く 失礼に当たるから……と、女房たちが申しましたので、一度か二度、御返事申し上げました。私はその他のことは存じません」と申し上げました。 薰大将は、 「こんな風に答えるだろう……とは思っていた。これ以上 無理に質問しても気の毒か……」と、つくづく物思いをして、 「匂宮のことを 珍しく心惹かれる方と、浮舟が思い申し上げても、わが方(薰)を さすがに疎かとは思っていないために 諦めることが出来ず、その頼りない心で、川の流れが近いのを頼りに、入水(丶丶)を思いついたのであろう……私がここに放っておかなければ、浮舟は酷い生活であっても、どうして深い谷を求めて 出ては行かなかっただろうに……何とも酷く辛い水の縁であることよ」と、この宇治川 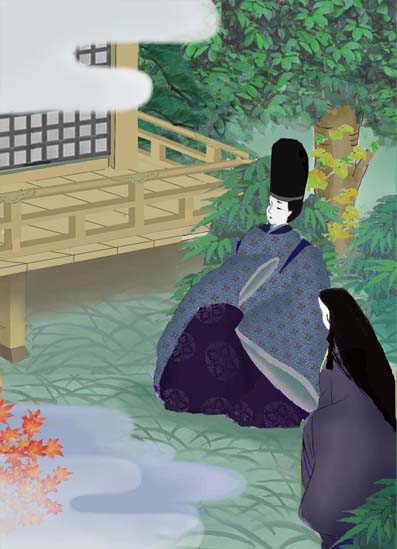 が疎ましく思われました。 が疎ましく思われました。長い年月、恋しく思っていた土地で、荒々しい山路の行き返りも 今はまた辛く、この里の名前 (宇治=憂し)でさえ、聞き辛い気持ちがなさいました。 「昔、中君が人形(ひとがた)と名付けたのさえ不吉で、ただ私の過ちのせいで 亡くなった姫君である」などと考え続けておられました。更に、母君が軽い身分で、娘の葬儀も風変わりに 簡素に済ませたことを、大層残念に思っておられましたが、 「母君は、どのように思っているのだろう……。その程度の身分の子としては、浮舟は大層素晴らしい女だった。匂宮との忍び事は知らないまま、この私との御縁を、どうお考えだったのだろうか」と、今は、様々に母君の心をお気の毒にお思いになりました。 穢れということではないけれど、供人の目もあるので、薰大将は 室内にもお上がりにならず、車の榻を召して、妻戸の前に座られるのも見苦しいので、大層茂った木の下の苔を敷物として、暫くお座りになりました。 「今は、この山荘を訪れるのも辛い……」と、周囲を見回しなさって、 我もまた 憂き古里を荒れ果てば たれ宿り木の影をしのばむ (訳)私もまた この嫌な古里を訪れずに 荒れ果ててしまったなら、誰が宿木のことを思い出すのだろうか…… あの阿闍梨は、今は律師になっていました。お呼びになって、浮舟の法事のことなどを命じて、念仏の僧の数を増やすなどさせなさいました。自殺の罪障はとても重いことをご心配なさって、 「軽くなるように、七日毎に読経し 御仏を供養するように……」等と 細々と仰いました。辺りが暗くなってきたので、京へお帰りになるのも「もし生きていたなら、今夜のうちに……」と、悲しくお思いになりました。 尼君にも ご挨拶をなさいましたが、辨尼は、 「自分がとても不吉な身だとばかり思い込み 沈んでいて、今は何も考えられず、ひどくぼっとして臥っております」と申させて 出てこないので、大将は 無理にはお立ち寄りなさいません。 道すがら、早くに浮舟を京に迎えなかった事が大層悔しく、川の音が聞こえる間は 心が騒いで、 「亡骸さえも探さずに、情けなく終わってしまったことだ。浮舟はどのような様子で、どこの川底の貝殻に混じっているのだろう……」と、心のやりどころがない程 苦しく思われました。 あの母君は、京で子を産む予定の娘のために、穢(けが)れを慎んで、いつもの家にも行かず 旅寝ばかりしていました。この悲しみを思い慰める時もないので、「またこの娘もどうなるのか……」と心配しましたけれど、やがて無事に出産したのでした。 母は穢れのため 娘の所に立ち寄る事もできず、残りの家族のことも考えられずに、ただ呆然と過ごしていますと、薰大将殿から御遣者が忍んでまいりました。何も考えられない心中でも、大層嬉しく有り難く思いました。 「あまりのことに、まずお見舞い申し上げようと思っておりましたが、心も落ち着かず 目も涙にくれた心地がして、『まして 子を思う親の心の闇に、どれほど惑わされておられることかと……』と躊躇われ、その時期を過ごして……儚く日数も経ってしまいました。世の中の無常を思うと、ますます心を鎮める方法もなくおりますが、思いの外に、私が命永らえましたなら、亡き浮舟の名残(縁者)として、必ず何かの時には、私を訪ねてください……」などと細かくお書きになって、御使者として 大蔵の大夫(仲信)を差し向けなさいました。更に、 「心のどかに いづれ浮舟を身近に……等と、様々な事を思いながらも、長い年月が経ってしまったので、必ずしも私を 誠意があるようには、見ておられなかったでしょうけれど、これからは、何事につけても、忘れ申すことはありません。またそのように、人知れず 思い置きください。幼い子供達もおられるそうで、内裏に伺候させなさる時には、必ず後見を致しましょう」等と、口頭でも仰いました。 母君は、 「娘の穢れなので、強く慎しまなくてもよい……。私は 深くは穢れに触れておりませんので…」等と言って、強いて仲信を呼び入れ、泣きながら 御返事を書きました。 「大層な悲しみにも 死ぬことさえできない命を、私は大層情けなく嘆いておりましたが、命永らえたのは、このような大将殿の仰せ言を拝見するためか…と思われます。 長年、娘の心細い様子を拝見しながら、それは私の人並みでない身の怠りのせいと存じておりましたが、畏れ多い御一言(ひとこと)を頂きまして……末永く頼りに思い申し上げておりましたが、娘が言う甲斐もないことになり、里の名(宇治=憂し)も、私には辛く悲しうございます。母・子供にまで 様々に嬉しい仰せ言に 命が延びるようで、もう暫く長生きしまして、やはり頼りに思い申し上げると思うにつけても、目の前の涙にくれて……今は何も申し上げられません」等と書きました。 御使者に、普通の禄などは見苦しく 不充分な気持ちがするので、この君(薰)に差し上げようと持ってきた立派な斑犀(はんさい)の帯や 太刀の素晴らしい物などを袋に入れて、仲信が御車に乗る時に、 「これは亡き人(浮舟)の御志でございます……」とお贈りしました。殿にご覧に入れると、 「思いがけないことだなぁ……」と仰いました。 仲信は、 「母君自らお会いくださり、大層泣いて いろいろな事を仰いました。幼い子供達のことまで 殿が仰せられたのは 誠にもったいなく、人の数にも入らぬ身分としては、かえって恥ずかしく思われますので、世間には何故(丶丶)という理由などは知らせずに……不出来な子供を皆、薰大将のところに参上させ、お仕えさせ申しましょう……」と言っておりました」と、報告申し上げました。 「誠に、後見するほどの縁続きではないけれど、帝にも、この程度の人の娘を差し上げたことがある。それに、その娘を寵愛するのを、人が非難すべきことであろうか。臣下では、卑しい女や、一旦嫁いだ女を 妻に持っている者も多い。『浮舟はあの守の娘であったか……』と人が噂しても、自分への取り成しが それで汚れるような形であるならともかく、一人の娘を亡くして悲しむ母親の心にとって、「やはり浮舟の縁でこそ、面目を保つことができたと分かる程度に、必ず心遣いをしてやろう……」とお思いになりました。 あちらでは、常陸の守が出て来て、立ったままで、 「こんな出産の時に、こうしておられるとは……」と腹を立てておりました。長い間、浮舟の居場所を知らせなかったので、守は「惨めな様子でいらっしゃる……」と思っていましたが、母君は、 薰大将が京にお迎えなさって後に、名誉なことだとして、守に報告しようと 思っているうちに、このように浮舟が亡くなってしまったので、今では隠すことも意味がなく、在りし日の様子を泣きながらお話し致しました。大将殿からの御文なども取り出して 見せますと、守は高貴な人を崇め、田舎者で 何でも誉める人なので、大層驚き 気後れして、御文を繰り返し見ては、 「大層 結構な幸福を捨てて 亡くなってしまった娘だなぁ……。私も、殿の家来として参上し お仕えしたこともあったが、最近は身近にお仕えすることもなく……殿は誠に気高くおられる方。私の幼い子供達についても仰せられたのは、何とも頼もしいことだ」などと喜ぶ姿を見て、母君は、 「浮舟が生きて居られたなら……」と大層悲しく、倒れ臥して 泣いてしまいました。 守も、今になって 泣いておりましたが、その反面、もし浮舟が生きていたならば、このような類の人を 殿がお訪ねなさる事は、決してなかったことでしょう。殿は、 「わが過ちにて、娘を亡くしたのもお気の毒なことだ。母君をお慰めしよう……」とお決めになり、 「世間の非難は、あまり考えるまい……」とお思いになりました。 四十九日(なななのか)の法事なども、薰大将がお世話なさるにつけても、「どういう事なのか……」とお思いにになり……いずれにしても 罪になることではないので……と、大層忍んで、あの律師の寺でおさせになりました。六十人の僧のお布施など、大がかりにお決めになりました。母君も宇治に来て、お布施を加えるなど致しました。 匂宮からは、右近のもとに、白銀の壺に黄金を入れて賜りました。人が見咎めるほどの大がかりな事はなさらずに、右近の志として供養しましたので、事情を知らない人は「どうして右近がこのような……」などと言いました。 殿は、供人たち親しい者ばかりを、多数差し向けなさいました。 「不思議なこと……噂にもならなかった女の法事を、こんなに立派にさせなさるとは……一体 誰なのか……」と、今になって 驚く人ばかり多かったのですが、常陸介が来て、主人のように振る舞うので、人々は「不思議なことだ……」と見ていました。守は、少将の子を娘に産ませて、盛大な御祝をさせようと目論んでいましたが、唐土・新羅などの装飾にも限りがあるので、家の中に無いものは少ないけれど、何か情けない感じがしました。更に 守は、 この法事については、人に隠れてひっそりと行おうと思ったけれど、気配が格別なのを見ると、 「もし生きて居られたら、私とは比較にならない程のご運勢であったのに……」と思いました。 宮の上(中君)も、亡き妹(浮舟)のために読経をおさせになり、七僧への饗応の行事もさせなさいました。帝も 今になって、「大将は、そのような女も持っておられた……」とお聞きになって、 「匂宮に遠慮申し上げて、大切に想っていた姫を隠しておられたのか……」と、お気の毒にお思いでございました。 お二人(薰、匂宮)の御心は、時が経っても悲しいものでした。残念な愛の最中に亡くなってしまっては、酷く悲しいことですが、匂宮の浮気な御心には「もしや慰められるのか……」との思いがあって、他の女に言い寄る機会なども、だんだん出てきました。 あの殿は、何やかやとご心配なさって、浮舟の周囲に残された人々をお世話なさったりして、やはり言う甲斐のない人(浮舟)を、忘れがたくお思いでございました。 后の宮(明石中宮)の御軽服(きようふく)(親族の喪に服する)の間は、宮は やはり六条院におられました。、二宮(匂宮の兄)が式部卿になられ、重々しくなられて、常には明石中宮方に参上なさいません。 匂宮は 何となく物寂しく悲しいので、一品の宮(女一宮)の御方を 慰め所にしておられました。そこには まだよくご覧になってない 器量の美しい女房たちが、数多く残っておりました。 大将殿が、かろうじて 大層忍んで 親しく話などなさっていた小宰相(こさいしよう)の君という美しい人で、性格の良い女房がおりました。琴を掻き鳴らす爪音や撥音も 人より勝っており、文を書き話などをすると、教養のある様子が添っていました。 匂宮も、長年 この小宰相にとても関心を寄せておいでになり、いつものように大将のことを悪く仰るのですが、「どうして……そのようにありふれた女ではないので、宮に靡くことはない……」と、気強く従わないので、真面目な人(薰)は「少し、他の女と違っている……」とお思いのようでした。大将が 最近 物思いしておられる様子を見て、小宰相はこっそりと 抑えきれずに、 あはれ知る心は人におくれねど 数ならぬ身に消えつつぞ経る かへたらば…… (訳)悲しみを知る心は人に劣りませんが、人数にも入らぬ身では、 消えんばかりに日々過ごしております。亡き方と代われるものならば…… と、由緒ある紙に書いておりました。何となく物悲しい夕暮れ、しんみりした頃でしたので、 「よくこちらの心を推察して 言ってきた心遣いも 悪くない……」とお思いになり、 常なしと こころ世を見る憂き身だに 人の知るまで嘆きやはする (訳)無常の世を見てきた嫌な我が身さえ、人が気づくまで嘆くのではないけれど…… この御歌をもらった喜びを「悲しい折に、とても嬉しかった……」と言い伝えたいと、大将は、 小宰相のところに立ち寄られました。大層傍にいて恥ずかしくなるほど堂々となさっていて、人柄もご立派で、普段は立ち寄られることがない、とても見窄らしい住まいである部屋の狭い遣戸口に寄り、座っておられますのを、体裁悪く思いながらも、さすがに卑下なさる様子もなく、とてもよい具合にお話など申しなさいました。 「亡き人よりも、この小宰相は奥ゆかしい感じがする。どうして宮仕えに出仕したのだろう。そのような女として、私の身近に置いたらよかったものを……」とお思いになりましたが、他人には見せない心の内は、お見せになりませんでした。 蓮の花の盛りに、明石中宮は御八講をなさいました。六条院の御ため、 紫の上の御ためなどと、皆、それぞれ日をお分けになって、御経や佛など供養なさいまして、厳粛に立派に行われました。 五巻目の日、大変な見物なので、あちらこちらの女房に付いて 見物に来る人が多くありました。 五日という朝座で終わって、御堂の飾りを取り外し、寝殿の調度品を改めるために、北の廂も障子などが取り外してあったので、女房たちは局に入っておりました。 部屋を整えている間、女一宮は、西の渡殿にいらっしゃいました。御経も聴き疲れて、女房たちも各々の局に下がっていますので、御前は人少ない夕暮れ、薫大将殿は直衣に着替えて、今日退出する僧にお話なさるべきことがあったので、釣殿の方においでになりました。既に僧達は皆 退出してしまって 人数も少ないので、池の方にて涼みなさいました。あの宰相の君などが、仮に御几帳などを立てて、ちょっと休む上局の方に行って、 「ここであろうか、衣擦れの音がするが……」と、馬道の方の襖障子が細く開いているところから、そっと中をご覧になると、女房の居るようないつもの気配でなく、広々と設えてあり、かえって几帳などが立ち違えてある辺りから、室内が見通せて丸見えになっていました。  氷を物の蓋の上に置いて、割ろうとして騒いでいる女房たち三人ほどと、童女とが見えました。 唐衣も汗袗も着ず、みな打ち解けた姿なので、御前とは思えないけれど、白い薄物のお召し物を着ていらっしゃる女一宮は、手に氷を持ちながら、女房達が騒いでいるのを少し微笑んでいらっしゃる御顔が、言いようもなく可愛らしく見えました。ひどい暑さは堪えがたい日なので、うるさい御髪が嫌だとお思いになってか、少しこちらに靡かせ引いていて、例えようもなく愛らしいご様子でした。 「美しい女性をたくさん見てきたが、似ている人はいなかった……」とお思いになりました。 御前の女房は 土人形のような感じがするのを、心鎮めて見ていますと、黄色い生絹の単衣に薄紫色の裳を着ている女が、扇をちょっと使っているところなど、いかにも嗜みがあるように見えました。 「氷を扱うのが難しそうです。ただそのままご覧なさいませ……」と、微笑んだ目元がとても愛嬌があります。その声を聞いて、これが探している人(小宰相)とお分かりになりました。 女房たちは無理をして氷を割って、それぞれの手に持ったり、頭の上に置いたり 胸にさし当てなどして、はしゃぐ者もおりました。小宰相は氷を紙に包んで、女一宮の御前にも差し上げましたけれど、宮はとても美しい御手を差し出しなさって、拭わせなさいました。 「いぇ、持てません。雫がたれて……」と、仰るお声が かすかに聞こえるのも、限りなく嬉しく、 「昔、まだ女一宮がとても幼くいらした頃、私が何も分からずお会いした時に、『なんと可愛らしい姫君か……』と拝見しました。その後はずっと御様子さえ聞かなかったのに……いかなる神佛がこのような機会をお見せ下さったのか……また、いつもの辛い物思いをさせようとする 神佛がおられるのか……」等と心乱れながら、女宮をじっと見つめて立っておられました。 こちら側の対の北面(きたおもて)に住む下臈の女房が、急ぎの用事で この襖障子を開けたままで局に下りてきたのを思い出し、人が見つけて騒いだら大変と思って、慌てて 簀子の方から戻ってきました。自分の姿が見られていることも知らずに……この直衣姿を見つけて「誰だろう……」と心騒いでいました。 薫大将はふと立ち去って「誰とも分かるまい。覗き見は 好々しいことだ……」と、物陰に隠れなさいました。 この女房(御許)は 「大変なこと。中が丸見えになるような御几帳の立て方をして……あの直衣姿は、左の大殿の公達でしょうか。疎遠な人なら ここまで来るはずもないけれど、何か噂でも立てば「誰が障子を明けたのか……」と必ず言い出すことになる……単衣も袴も生絹のように見えたお姿だったので、誰も衣擦れをお気づきにならなかったのでしょう……」と困っておりました。 薰大将は、 「だんだん聖になっていった心を、大君のことで一旦道を踏み違えて、様々に物思いする人となってしまった……その昔に出家していたなら、今は深い山に住み着いて、このように心乱すことはなかっただろうに……」などと思い続けると、なお 心落ち着きません。 「どうして長年、女一宮を拝見した…と思っていたのだろう。(今になって心惹かれても)かえって苦しいだけで、何の甲斐もないことなのに……」とお思いになりました。 翌朝、お起きになった女二宮の御器量がとても美しいので、 「この宮より きっと女一宮は勝っておられるのか……」と思いながらも、 「まったく似ておられない。驚くほど上品で美しく、言葉にならないほどのご様子。一つには気のせいか、時節柄なのか……」とお思いになって、 「とても暑いね。これよりもっと薄いお召し物になさい。女はいつもの様でない物を着るのこそ、その折々につけて美しいものです」として、 「あちらに行って、大弐に、羅の単衣の着物を縫って差し上げるように言いなさい」と仰いました。御前にいた女房は、「女二宮のご器量が大層美しい盛りにいらっしゃるのを、殿がさらに引き立てようとなさる……」と面白く思っておりました。 殿は、いつもの通り 念誦なさる部屋においでになって、昼頃になって再び、女二宮のところにお渡りになりますと、先ほど仰ったお召し物が御几帳に打ち掛けてありました。 「どうして これをお召しにならないのですか。人が大勢見る時に 透けたものを着るのは下品に思われるけれど、今なら構わないでしょう……」と、ご自身で女宮にお着せになり、御袴も 昨日と同じ紅色になさいました。御髪の多さや裾などは、女一宮には負けないけれど、やはりそれぞれの美しさなのか、似るはずもありません。氷を持って来させて、女房達に割らせなさいまして、ひとつ手にとって女二宮に差し上げて、ご自分の心中も楽しくなられました。 「絵に描いて、恋しい人を見る人はいないだろうか。ましてこの宮は、我が心を慰めるには 相応しくない 御姉妹でおられる……」とは思うけれど「昨日は あのように、私も宮たちの中に混じって 心ゆくまで拝見することができたなら……」と思い、心ならずも 残念だとお思いになりました。 「最近、女一宮にお手紙など差し上げなさいましたか」とお尋ねになりますと、 「内裏にいた時に、帝がそう仰いましたので、お手紙を差し上げましたけれど、長い間 そうしていません……」と仰いました。 「臣下になられたからと言って、女一宮から御文を下さらないのは 情けないことです。今、大宮の御前にて『姉宮をお恨み申されています……』と申し上げましょうか」と仰いますと、女二宮は、 「どうしてお恨みなど申し上げていましょう。嫌なことを……」と仰いますので、 「低い身分になったから 見下していらっしゃるように思えるので、こちらからはお便りしないのですと申し上げましょう」と仰いました。 その日はずっと女宮とお過ごしになって、翌朝、大宮に参上なさいました。いつものように匂宮もおられまして、丁子色(黄色)に深く染めた薄物の単衣を、濃い縹色(藍色)の直衣の下にお召になり、とても素晴らしいお姿でした。女一宮が美しかったのに劣らず、白く美しく、やはり以前より面痩せなさったご様子は、大層 見る甲斐のあるものでございました。 「女一宮と似ておられる……」と、匂宮を見るにつけても、まず女宮が恋しく思われるのを、 「誠にけしからぬこと……」と心鎮めて、むしろお逢いしなかったよりも辛い…とお思いでした。 匂宮は絵を沢山持たせて、大宮方に参上なさいましたが、女房を介してあちら(女一宮方)に差し上げなさって、ご自分もお渡りになりました。 薫大将も、大宮の近くにお寄りになりまして、御八講が立派に行われたことや、昔のことなどを少しお話申し上げながら、残っている絵をご覧になるついでに、 「私の所におられる皇女(女二宮)が、宮中から離れて 思い沈んでいらっしゃるのが、私にはお気の毒に拝されます。姫宮(女一宮)の御方より、お手紙もありませんことを、このように身分が低いところに嫁がれたために、女一宮がお見捨てなさったように思えて、気が晴れないようでございますが、 このような絵などを、時々お見せくださいませ。私が持って参りますのも、また張り合いのないものでございましょうから……」と仰いますと、大宮は、 「不思議なことを……どうしてお見捨てなど申しましょう。内裏は近かったので、時々、お手紙などやりとりなさったようですが、別々になられた折に、滞るようになったのでしょう。これから女一宮に手紙を書くようにお誘いしてみましょう。そちらからも どうしてお手紙なさらないのでしょうか」と申しなさいました。 「こちらからはどうしてできましょうか。もとより人並みに扱っていただけなかったとしても、私がこのように親しくお仕えする御縁によせて、心を懸けてくださいますのは、嬉しいことでございます。それ以上に、親しく慣れておられましたのに、今お見捨てなさるのは 辛いことでございます……」と申し上げました。大宮は、薰大将に「好色な下心がある……」とはお思いになりませんでした。 御前を退出なさって、「昨夜の気がかりな人に逢いたい……先日の渡殿を心慰めに見よう……」とお思いになって、御前の西側の方向に行かれますのを、御簾の内の女房は、特に心遣いをしていました。誠に、薫大将は大層御姿がご立派で、優雅な身のこなしでおられます。渡殿の方では、左の大殿(夕霧)の公達などがおられて 話をしている気配がするので、妻戸の前にお座りになって、 「幾度も参上致しますが、こちらの御方にお目にかかることは難しうございますので、いつの間にか老人のような気持ちがいたします。今からは…と気持ちを奮い起こして……若い人たちは不似合いな振る舞いだと思うでしょう……」と、甥の公達の方をご覧になりました。 「今からお馴れになれば、なるほど若々しくなられるでしょう」などと、とりとめのないことを言う女房たちの気配も、不思議と優雅で、まさしく情緒のある御方の雰囲気でございました。特に用事もないけれど、薫大将は世間話などしながら、物静かに いつもよりは長居をなさいました。 姫宮(女一宮)は、明石中宮方にお渡りになりました。大宮が、 「薰大将がそちらにおいでになったのでは……」とお尋ねになりますと、大納言の君が、 「小宰相の君に何か仰ることがある……ということでしょう」と申し上げました。 「いつも真面目な人(薫)が やはり女性に心を留めてお話なさるのは、心の内も見ておられるのでしょう。相手が気の利かない女でしたら困りますが、小宰相なら とても安心できます……」と仰って、ご姉弟でありながら、この君(薫)をやはり気恥ずかしいほどにご立派に思って、 「女房もきちんと心遣いして、応対をするように……」とお思いでございました。 「大将殿は、他の女房よりは 特に小宰相に心を寄せなさいまして、局などにもお立ち寄りなさるようです。お話などを細かになさって、夜更けて退出なさる時もありましたけれど、普通のありふれたお通いではないのでしょう。匂宮を『とても情けなくおられる…』として、小宰相はお返事さえ申し上げないようです。恐れ多いことですが……」と言って笑いますと、大宮もお笑いになって、 「匂宮の大層見苦しい御性格を よくご存知なのが面白いことです。どうにかして 匂宮のこのような御癖を止めさせ申したいものです。誠に恥ずかしいこと。この女房たちの手前……」と仰いました。大納言は、 「そう言えば、とても不思議な事を聞きました。この大将殿が亡くしなさった人(浮舟)は、匂宮の二条の北の方(中君)の御妹君ということです。異腹なのでしょう。前の常陸の守の妻を、叔母とも 母とも言っているのは どうなのでしょうか。その姫君のところに、匂宮が大層忍んでお通いになったことを、大将殿が聞きつけなさったのでしょう。急いでその姫を京にお迎えなさろうと、邸の番人を増すなど厳重になさいましたので、匂宮は大層忍んで宇治にお通いになりましたのに、邸にお入りになることもできず、粗末な御姿に身を窶し 御馬に乗り立ったまま、京にお帰りになりました。 姫君も匂宮をお慕い申し上げていたのでしょうか。急に姿を消してしまいましたので『川に身を投げたようだ……』と、乳母等が泣き惑っておりました」と、お話し申し上げました。 大宮は、誠に呆れたこと…とお思いになって、 「誰がそのようなことを言うのでしょう。お気の毒で とても情けないことです。これほど珍しいことは、自然と噂に立つでしょう。大将も そのようには仰らずに、世の中の儚く無常なこと、宇治の八宮の一族の御命が短かったことこそを、ひどく悲しんでおられた……」と仰いました。 「下衆は確かでない事でも言い出すようですが、宇治に仕えていた下童が、つい最近 小宰相の実家に出て参って、確かなことのように言いました。 「このように不思議に亡くなったことは、誰にも聞かせてはならない。大袈裟で気味悪い話として、ひどく隠していたことなので、薫大将殿にも詳しくはお聞かせ申さなかったのでしょう……」 大宮は、 「まったく、このようなことは 決して他人に話さぬように、皆にも言いなさい。このような男女の話で、匂宮が御身を過ち損ない、他人から、軽々しく配慮のない者 と思われることになりましょう」と、大層ご心配なさいました。 その後、女一宮の御方より、二の宮にお手紙がありました。筆跡などの大層美しいのをご覧になって、薫大将はとても嬉しく思われ、 「このようにしてこそ、もっと早く見るべきだった……」とお思いになりました。 興味深い絵などを 沢山、大宮から二宮に頂戴いたしました。大将殿は、それにも勝る面白い絵などを集めて宮に差し上げました。古い物語にある 芹川の大将が、とお君の女一宮に思いを寄せている秋の夕暮れに、思い余って出かけていった場面が興味深く描かれている絵をご覧になって、大将は、 「とてもよく わが身に思い当たる……これほど思いを寄せてくれる女性が、私にもあったなら……」と思うのこそ、情けないことでございます。 萩の葉に露吹きむすぶ秋風も 夕ぞわきて身にはしみける (訳)萩の葉に露が結んでいる。吹く風も夕方には特に身にしみて感じられる と、書き添えたいと思われましたが、そのような少しばかりの気配さえも漏らしたなら、大層煩わしくなる世間なので、ほんの少しの気持も仄めかすことができません。このように、万事にいろいろと物思いした後に、 「もし亡き大君が生きておられたら、どうして外の女に 心を分けたりしましょうか。今上帝の内親王を賜うとしても、お受けはしなかったろう。また、帝が「心寄せる女がある……」とお聞きになっていたら、このようなこともなかっただろう……やはり情なく 私の心を乱しなさる宇治の橋姫だ……」と思い余って、また宮の上(中君)にも心奪われて、恋しく切なくどうしようもないこの身を、疎かに思うほど 悔しいことでございました。 中君に想いを寄せ、その次は 呆れる有様で亡くなった浮舟の心が とても幼く、入水を思い止まることができなかった軽率さを、恨めしく思いながら、 「やはり大変なことになった」と、浮舟が思い詰めていた時に、私の態度がいつもと違っている…と、良心の呵責に苛まれて 嘆き沈んでいたご様子について、右近から聞いたことを思い出されて、 「重々しい方という扱いでなく、ただ気楽に愛らしい相手として、傍に 置いておこう…と思ったのに、本当は大層可愛らしい人だった……」と思い続けると、とても辛くなられました。 けれども「匂宮を恨み申すまい。浮舟を酷いと思うまい。ただ わが人生が 世間離れしていることが 間違いなのだ…」などと、ずっと長い間 物思いに耽っておられました。 心穏やかで 御姿も素晴らしい人(薫)でさえ、このような男女のことについては、見苦しいことが自然と出てくるのを、匂宮は まして慰めがたくお思いになって、浮舟の形見として 尽きない悲しみをお話しする相手さえいないけれど、対の御方(中君)だけは「お気の毒に……」等と仰るけれど、深く親しんでお付き合いなさった方でもなく、短い交際だったので、悲しみが深いとはどうしてお思いになろうか……また匂宮はお心のままに「恋しい悲しい……」等と、中君に仰るのは心痛むので、宇治にいた侍従を、例によって二条院にお迎えになりました。 女房たちは皆、散り散りになってしまいました。乳母とこの侍従を、浮舟が特に目をかけて下さったことも忘れがたく、この侍従は身内外の女房だけれども、やはりとても親しい話し相手として 過ごしていました。他にはあり得ない程の宇治川の音にも「いつの日か 何か嬉しいこともあろうか……」と、信じていた頃には慰められていたけれど、今は辛く大層恐ろしくのみ思えて、京の粗末な所に、 最近引っ越して来ていました。それを、匂宮は捜し出しなさって、 「それなら、ここにお仕えなさい……」と仰いました。けれども侍従は、 「御心は有り難いのですけれど、女房たちが噂することも、そのような筋の話が混じるので、聞きにくいことになろうか……」と躊躇われ、お引き受け申し上げませんでした。結局、 「后の宮にお仕えしたい……」と希望しましたので、匂宮は、 「良いだろう。それでは人知れず目をかけてやろう……」などと仰いました。 侍従は、心細く頼りどころのない身でも、慰められることがあろうか……と、縁者を求めて、明石中宮方へ出仕することになりました。女房達は「きちんとした佳ろしき下臈だ」と心許して、非難することもありませんでした。 薫大将殿が、常に中宮方に参上なさるのを見るたびに、しみじみ感慨深く思われました。女房が、 「ここは、高貴な姫君ばかりが参り集まる官邸です……」と言うので、 だんだん目に留めて見回しましたが、あの浮舟に似た美しい姫君は いないようでした。 この春、亡くなられた式部卿宮の御娘を、継母・北の方は 特に可愛がることはありませんでした。兄の右馬頭で人柄も格別なところがない者が、この娘に思いを寄せていたので、継母は 可哀想とも思わずに縁づけたことを お聞きになって、大宮は、 「お気の毒に……父宮が大層大切になさっていた宮の君を、つまらぬ者にしてしまった……」などと仰せになったので、宮の君は大層心細く 嘆いていらっしゃいました。御兄の侍従も 「優しくこのように 大宮が仰ってくださるものを……」として、最近、その宮の君を 大宮方に迎え取らせなさいました。姫宮(女一宮)のお側に仕える者として、誠に最適なご身分の人なので、高貴で格別の扱いで伺候なさいました。決まりがあるとは言え、宮の君などと呼ばれて、裳などを引き掛けなさるのが、とてもお気の毒でございました。 匂兵部卿の宮(匂宮)は 「この宮の君は、恋しい人(浮舟)に関わりのあるご様子をしているだろうか。父親王は、浮舟の父・八宮の兄弟なのだから……」などと、いつもの御心で 浮舟を恋慕いなさるにつけても、宮の君を知りたいと思う御癖が止まずに、いつの日か…と、御心にかけておいでになりました。 薫大将は、 「なんとも非難したい気がする人だなぁ。父宮は、昨日今日の内に、この宮の君を春宮に差し上げようか……などとお思いになり、私にもそのように仄めかされた……。このような無常の世の衰退を見ると、水の底に身を沈めても、非難されないだろう……」などと思いながら、誰よりも心を悩ませ申し上げておられました。 暑さを避けて、明石中宮は この時期 六条院におられますので、内裏よりも広く趣があり住みよい所として、いつもは仕候していない女房たちも大勢 寛いで移り住み、広々と沢山ある対屋、渡廊、 渡殿などで 過ごしておりました。 左大臣殿(夕霧)は昔の威勢にも引け劣らず、総てこの上なく 中宮にお仕え申しておられました。大層 重々しくなられた御一族なので、かえって昔よりも 今風で華やかさは勝っておりました。 この匂宮は、いつもの御心ならば、幾月かの間に どのような好色事でもなさっておられましたが、この頃は静かになられて、人目には「少しは大人になられて、御癖もお治りになった……」と見えましたが、最近はまたご本性を現して、宮の君に関わろうと 歩き回っておいでになりました。 「涼しくなった……」として、明石中宮は 内裏に帰参なさろうとするので、 「秋の盛り、紅葉の頃を見ないのは心残りで……」などと、若い女房たちは残念がって、六条院に参集する頃でした。池水に親しみ 月を愛でて、管弦の遊びが絶えず催され、いつもより趣あるので、 匂宮は、やはりこの方面では 大層もてはやされておられました。朝夕見慣れていても、宮はやはり 今見た初花のように美しくおいでになりました。一方、大将の君は、あまりそれほど遊びには参加なさらないので、「こちらが気恥ずかしくなるほど きちんとした方だ……」と、女房たちは皆 思っていました。 いつものようにお二人(匂宮と薫)が参上なさって、中宮の御前におられます時に、あの侍従が 物影から覗いて拝見しながら、 「どちらかの方にでも縁付いて、浮舟が 幸運な運命に思える御様子で、この世に生きておられたなら……入水なさるとは 呆れるほど儚い情けない御心だったことよ……」などと、他人にはその辺りの事については知らん顔で、何も言わずに 自分の心一つで、尽きせず胸を痛めておりました。 匂宮は内裏のことなどを、中宮に細やかにお話申し上げなさるので、もう一方(薫)は退出なさいました。侍従は「見つけられないようにしよう。暫くの間は、浮舟の一周忌も待たずに、宮仕えとは 薄情な人だ…と思われたくない」と、身を隠しました。 東の渡殿の開いている戸口に、女房たちが大勢いて、話などひっそりとしているところに、薫大将殿がおいでになりました。 「誰のことを 親しく思うべきか……女でさえ、私のように安心できる人はありません。私は、役に立つこと等を、貴女たちに教えてあげられることもあります。だんだん私をお分かり下さるなら、とても嬉しいことです……」等と仰いますと、女房達はとてもお答えし難く思っておりました。その中で、辯の御許といって、物馴れている年配の女房が、 「そのように、親しくすべき理由のない者こそ、気兼ねなく振る舞えるのではないでしょうか。物事とはそのようなものです。必ずしもその理由を調べた上で、貴方に打ち解けられるものでもありませんが、これほど厚かましさが身についた私が 引き受けないのも 心痛みます」と申しますと、 薫大将は、 「恥じる理由はあるまい…と決めていらっしゃるのが、残念なことです」と仰りながら、辯の御許を見ますと、唐衣は脱いで押しやって、寛いで手習いしていたのでしょう。硯の蓋に置いて、頼りない花の枝先を、手折って弄んでいたように見えました。ある者は几帳の陰ににすべり隠れ、またある者は背を向けて、押し開けた妻戸の方に隠れながら座っておりました。大将は、その髪の形を美しいと見渡しなさって、硯を引き寄せて、 女郎花(おみなえし)みだるゝ野辺にまじるとも 露のあだ名を我にかけめや ……心やすくは思(おぼ)さで (訳)女郎花の咲き乱れる野辺に迷い込んでも、露に濡れたという噂を 私にお立てになれましょうか。 ……どなたも気を許してくださらないので… と、ただこの襖障子に後向きにいた女房にお見せになりますと、すぐに 身動ぎもせず落ち着いて、 花といへば名こそあだなれ女郎花 なべての露に乱れやはする (訳)花といえば名前こそ好色に聞こえますが、普通の露に乱れたりしません。 書いた筆跡は、ただ一首ながら風情があって無難なので、「誰なのだろう」とご覧になりました。「今、参上した途中で、道を塞がれてここに留まっていたようだ……」と思われました。辯の御許は、 「本当にはっきりした老人のようなお言葉。憎うございます……」と言って、 旅寝して猶こころみよ女郎花 さかりの色に移り移らず (訳)旅寝して、試してみてください。女郎花の花の盛りに、お心が移るか移らないか…… そして 後でお決め申しましょう」と言うので、薰大将は、 宿貸さば一夜は寝なん大方の 花に移らぬ心なりとも (訳)宿を貸してくださるならば、一夜は泊まってみましょう。普通の花には 移らない私の心なのですが…… 辯は「どうして恥をかかせなさいます。普通の野辺の洒落を申し上げただけですのに……」と申しました。大将はちょっとしたことを ほんの少し仰るので、女房たちは残りを全部聞きたい…とばかり、思い申し上げておりました。 「思慮が足りなかった……道をあけますよ。特に今日は 恥ずかしがっている理由がありそうな折ですから……」と仰って退出なさいますと、「大体は 奥ゆかしいところが無いだろう…とお思いになるのこそ辛いことです……」と思う 女房もおりました。 東の高欄によりかかって、薫大将は夕日が影るにつれて、花の咲き乱れる中宮の御前の草むらを見渡しなさって、何となくしみじみとお思いになり、 中んづく はらわた断ゆるは 秋の天 (訳)とりわけて腸の断ち切れる思いがする秋の空だ…… という詩句を、大層忍んで朗誦なさりながら 座っておられました。先程の衣擦れの音がはっきり聞こえる気配がしました。母屋の襖障子を通って あちらに入っていくようです。 匂宮が歩いておいでになり、 「ここから あちらに参ったのは誰ですか」とお尋ねになりますと、女房が、 「女一宮の御方に仕える 中将の君です」と答えました。これをお聞きになって、 「やはりけしからん振る舞いだ。その女を思い寄る男に、誰だろうか…と尋ねられた時、このように遠慮もなく名前を教えてしまうとは……この匂宮には、女房たちが皆 馴れ馴れしく思っているようなのも 残念なことだ……」とお思いになり、 「無遠慮で 身勝手なお振る舞いに、女はきっと負け申してしまうのだろう。私は残念なことに、宮の御一族には、妬く 残念なことばかりがある身のようだ。何とかして、この辺りには珍しいような美しい女で、例によって宮が熱中して騒いでおられる女を、この私が口説き落として……私が経験したように……匂宮に『安心できない男だ』と思わせ申したいものだ。本当に分別を弁える女なら、私の方に寄ってくるはずだ。けれども難しいことだなぁ、女の心は……」とお思いになりました。 対の御方(中君)に対する宮のお振る舞いを、親王として相応しくないものと思い申し上げながら、ご自身が大層不都合な 好色な気持になっていくので、 「世間の評判を辛いと思うけれど、やはり放っておくことはできない……しかし、私の気持ちに 中君がお気づきになるのは 有り得ないことだし、お気の毒なことでもある。 中君のようなご性格の方は、この辺の中に居るだろうか。女房たちの間に立ち入って 深く見てはいないので 分からないことだが……寝覚めがちに所在ないので、私も少しは好色なことも 習ってみたいものだ……」等とお思いになりました。けれども やはり、今は 相応しくないようでした。 あの西の渡殿に、先日を真似て、薫大将が わざわざおいでになったのも 不思議なことでした。 女一宮は、夜は明石中宮方にお渡りになりましたので、女房たちは月を観るとして、この渡殿に 寛いで集まり 話などしている時でした。箏の琴をとても優しく弾く爪音が 趣深く聞こえました。 大将は、思いがけない所にお寄りになって、 「どうしてこのように妬ましそうに 掻き鳴らしなさるのでしょうか」と仰いますと、女房たちは皆、驚いたようだけれど、少し巻き上げた御簾を下ろしなどもせず、起き上がって(故事を引用して) 「似ている兄様がおりましょうか」と 答える声は、中将の御許という人でした。大将は、 「私こそが、御母方の叔父です」と、戯れ事を仰って、 「いつものように、中宮方に女一宮はいらっしゃるようですね。どのようなことを、この里住みの時には なさっておいででしょう」と、たわいもないことをお尋ねになりました。 「どこにいらしても 同じことでございます。女一宮はただこのようにお過ごしでございます……」と答えますと 「結構な御身分の方だ……」と、気のない溜息をうっかりしてしまったので、「変だ……」と思う人があっては…と紛らわすために、女房が差し出した和琴を、ただそのまま掻き鳴らしなさいました。律の調べは、不思議とこの季節に合うように聞こえる音なので 心地好く、最後までお弾きにならないのを「かなり良い調べ……」と心惹かれた女房たちは、とても残念に思いました。 「わが母宮も女一宮に劣りなさる方だろうか。后腹と申し上げる程度の差があるけれど、帝が大切になさる様子に違いはない……。やはり女一宮の辺りは、とても格別な感じがするのは 不思議なことだ。明石の浦は心憎い所だなぁ……」等と思い続ける中で、 「私の運命は、とてもこの上ないものであった。その上に、女一宮をも 並べて頂戴していたら……」と思うのこそ、大層難しいことでございました。 宮の君(亡き式部卿宮の御娘)は この西の対にお部屋を持っておられました。その周辺には、若い女房たちが大勢いる気配がして、月を愛でておりました。 「あぁ、お気の毒に……この宮の君も同じ皇族であるのに……」と、薫大将は 思い出し申し上げて、 「父・親王が昔、お心をお寄せになったものを……」と言って、宮の君方へおいでになりました。 可愛らしい宿直姿の童女が二、三人出てきて、歩き回っていました。大将のお姿を見つけて、御簾の内に入る様子などが恥ずかしげでした。「これこそ、世の常のこと」とお思いになりました。 南面の隅の間に立ち寄って、咳払いをなさいますと、少し年配の女房が出てきました。 「人知れず宮の君に心を寄せており……」などと申し上げますと、女房たちは皆 「言い古した言葉を 初々しい様子で真似ている……」と思うようでしたが、 「私は真面目に、言葉より外のことを 求められるようです」と仰いますと、女房は、宮の君に言い伝えもせずに、利口ぶって、 「誠に、思いもかけなかった宮仕えの御様子につけても、故父宮がお考えになっておられたことなどが思い出されて……このように折々にふれて申し上げる『陰ながらの言葉』もお喜び申し上げていらっしゃるようです」と申しました。 「世間並みの扱いのようで、失礼ではないかと……」と、薫大将は辛いので、 「昔から 見捨てられない間柄としてよりも、今は、まして宮仕えのことにつけても、私を思い出して 訪ねてくださったら 嬉しく思います。よそよそしく 人を介してなどで 私をお扱いなさるならば、 お応えはできません」と仰いました。女房は「誠に……」と慌てて気付いて、宮の君を揺さぶるようなので「松も昔の知る人もなし……」と、物思いに沈んでしまわれ、 「もとからの御縁と仰ることは、真面目に とても頼もしく存じられます」と、人伝ではなく仰る声が、とても若々しく愛嬌があって、優しい感じが添っていました。ただ、普通の局に住む人と思えば、大層趣があるご様子に違いないけれど、ただ今は、 「どうして ほんの僅かでも、人に声を聞かせてもよいという立場に、馴れてしまわれたか……」と、心痛く思われました。 「ご容貌なども、とても優美であろうか……」と、宮の君のお姿を見たい感じがしましたが、  「この人はまた、例によって、あの匂宮の御心をも 乱すもとになるだろう……」と、興味深く、滅多にいない方だと思っておられました。 「この人はまた、例によって、あの匂宮の御心をも 乱すもとになるだろう……」と、興味深く、滅多にいない方だと思っておられました。「この宮の君こそは、高貴なご身分の父宮が 大切にお育てなさった姫君だ。また、この程度の女なら他にも多くいるだろう。けれども不思議であったことは、あの聖(八宮)の周辺、宇治の山懐から出てきた姫君(大君・中君)で、不完全な人は居なかったことだ。 この頼りない軽率と思われる人(浮舟)も、ちょっと逢った感じでは、大層素晴らしかった……」と、何事につけても、ただあの八宮の一族を 慕わしく思い出しなさいました。 「不思議とつらいご縁であった……」と、つくづく感慨深く思い続け、物思いに耽っている夕暮れ、 蜉蝣(かげろう)が頼りなく飛び交っているのをご覧になって、 ありと見て手には取られず、見れば又 ゆくへも知らず消えし蜉蝣(かげろう) ……あるかなきかの (訳)そこにいると見えても手に取ることはできない。 見えたと思うとまた行方知れずに消えてしまった 蜉蝣のような人(浮舟)よ ……いるのか いないのか…… と、例の通り、独り言を仰ったとか。 ( 終 ) 源氏物語「蜻蛉」(第52帖) 平成29年初秋 WAKOGENJI(文・絵) 目次に戻る |